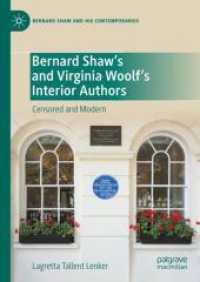内容説明
革命で激変したロシア社会―ひしめきあって暮らす労働者や都会に流れ込んできた地方出身者は、背伸びして、つっぱって、ちょっと無理して生きていた。やることなすこと滑稽で、ばかばかしいけど、どこかペーソス漂う、どこにでもいそうなオジサンたちや、奥様気取りのオバサンたち。そんなロシア庶民の日常を独特の語り口で切り取って見せてくれるゾーシチェンコ。ゾーシチェンコを愛してやまないロシアの画家のイラストをふんだんに使って、翻訳困難と言われたユーモアの世界を日本ではじめて単行本化。
著者等紹介
ゾーシチェンコ,ミハイル[ゾーシチェンコ,ミハイル][Зощенко]
1894年ペテルブルグに生まれる。ペテルブルグ大学法学部を中退後、第一次世界大戦に参戦、勲功をたてるが、毒ガスに侵され除隊。この後遺症に生涯苦しんだ。1918年には赤軍に入隊、翌年除隊。様々な職を転々としながら文学を志し、1921年に文学サークル「セラピオン兄弟」に参加し、本格的な文芸活動を開始する。民衆の言葉をたくみにとりいれた独特の文体を確立、20年代後半から30年代にかけてユーモア作家として絶大な人気を博したが、1946年のジダーノフ批判で「反社会的」だと批判され、作家同盟から除名された(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
72
鬱病に悩み、スターリン批判者として作家としての道を閉ざされた不遇な作家、ゾーシチェンコ。でも彼の作品には優しい眼差しと生き生きと日々を過ごすお調子者などの市井の人々が闊達且つユーモラスな語りで生きていました。「貴婦人」の貴婦人のいけ好かなさに「あるある」と頷き、表題作に笑いつつもしんみりし、「茅はさやぐ」の酔っ払い神父が引き起こすハチャメチャな葬式に爆笑。「結婚にまつわる出来事」の「結婚したがる人には理解に苦しむ」には激しく、同意。そして「リョーリャとミーニカ」のおはなしが心に沁みます。パパさん、良い人。2016/07/08
Nobuko Hashimoto
19
『8号室ーコムナルカ住民図鑑』の作者コヴェンチュークが大好きだという作家の掌編小説集。小咄ほどにも至らないような、ソ連初期の庶民のちょっとした日常を綴ったもの。翻訳者によれば、インテリを真似た、でも非なる滑稽な言葉遣いが面白さの肝なのだそうだが、翻訳ではそれは伝わらず、私の笑いのツボとはちょっと合わなかった。が、本書の挿絵も描いているコヴェンチュークによるエッセー「ゾーシチェンコを偲ぶ会」や翻訳者の解説が本編よりも興味深かった。超人気者から「人民の敵」へと貶められた不遇の作家の人生に俄然関心が高まった。2022/01/25
くさてる
13
ロシア人作家、革命直後、くらいの前知識しかなく読み始めたが、短く読みやすいユーモアが見え隠れする感じの良いお話ばかりで、いいなあ、こういうの、と素直に思いました。登場人物みな、可愛らしいくらいに素直で正直で、適度にこずるくみっともないけど、楽しく生活している感じ。しかし最後の「ゾーシチェンコを偲ぶ会」で、作家の辿った道を知ると、その印象に哀しい暗い色が差してしまった。作品の価値には何の関係も無いことだが、政治が介入する醜さに辛い思いになりました。挿画がとても素敵です。2014/09/03
きゅー
9
いかにもロシアらしい、アネクドート(滑稽な小話)だった。当然ウォッカの飲み過ぎも出てくるし、アジ演説も出るし、組織からの無茶苦茶な指示とそれを無視するプロレタリアートの姿も出てきており、非常にオーソドックスな小話集だった。こういった小話は多くの作家が同じようなものを書いているため、作家の際立った特徴が感じられない反面、安心して読める。スワヴォーミル・ムロージェク、ヤン・ネルダ、セルゲイ・ドヴラートフ辺りのファンであれば、文句なしにツボなのでは。2012/06/21
mejiro
8
ソビエト社会を風刺した作品として読むと刺激が弱め。どこかで読んだような内容でガツンとくるものはなかった。温かみのある笑い話といったほうが合ってるかも。本書が出版された経緯が興味深かった。2015/03/29