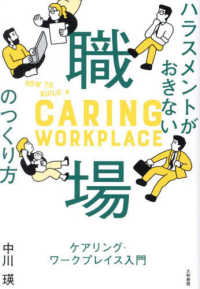内容説明
宮台真司×大澤真幸、“10年代の世界”へ向けて初対談、ついに実現。
目次
対談 正義は可能か?(宮台真司×大澤真幸)(善と正義の違い;「市場か再分配か」は遅れた議論;「みんな」は本当は「みんなで」ではない;沖縄の自己決定的な自立;資本主義の持続可能性 ほか)
論文 二つのミメーシス―宮台真司の論を手がかりにして(感染的模倣;「理想自我」と「自我理想」;利他的行為の倒錯;もうひとつのミメーシス)
著者等紹介
大澤真幸[オオサワマサチ]
1958年生まれ。社会学博士。『THINKING 「O」』主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
- スライセンジャー&フォートラン胃腸・肝…
-
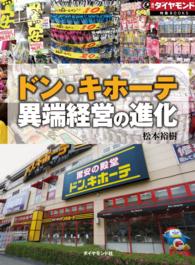
- 電子書籍
- ドン・キホーテ 異端経営の進化 週刊ダ…