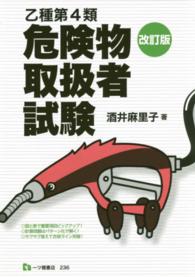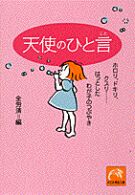感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
oDaDa
4
相当な良書。「西欧諸国の政府はもはや福音書を広めようとはしない。代わりに芸術を広めようとしている。」ここでもまた国家装置としての「美」の殿堂である美術館は、最早神殿である。「芸術は典型的な価値材である。」「芸術は「宗教」の現代版なのである。」この本の構成は素晴らしく、やや冗長に思われる節もあるが、それだけに徹底的な考察がなされている。ビジネスライクな薄っぺらい本には到底興味を持てないから、経済人の書く本にアレルギーがあったが、これは別。芸術活動に対してもリアルで望まねばならないと思わされるであろう。2022/12/21
よく読む
2
芸術価値と市場価値は一致しない。「芸術は神聖で、芸術家は無私で活動する」という神話を誰もが共有している。昔は芸芸術家の数は制限されていたが、二次大戦後に増大した。さらに、敗残者を救う政府の助成金まである。芸術家は供給過剰となっている。助成金は、作品製作のコストを上げてしまう。大多数の芸術家が貧乏である原因にもなっている。芸術は国策にもなり、その国の美術館に外国から人がやってくることもあるので、政府は贔屓な芸術を推進しようとする。助成金はやめた方がよい。また、ハイ・アートとロー・アートの差は縮みつつある。2017/03/23
Go Extreme
1
神聖な芸術:誰が芸術を定義する権力 経済の否定:なぜ芸術への贈与は称賛される 「敬愛的価値」対「美的価値」:質に対する金銭的報酬 無私で奉仕するアーティスト:アーティストは報酬を志向 アーティスにとってのマネー:アーティストは誤った情報を与えられたギャンブラー 構造的貧困:助成金や寄付は貧困を増大 コスト病:助成が必要 与える権力と与える義務:なぜ人は芸術に贈与する 政府は芸術に奉仕:芸術への女性は公共の利益に奉 非公式の障壁:芸術はどれくらい自由か 残酷な経済:芸術という例外的経済 芸術の経済の未来2022/11/12
アムア
1
アート作家兼経済学者の経歴を持つ学者が書いた本。文章は全体的に硬いのでアート関連本の中では読みにくい部類。アート作家の半数は赤字経営。なぜアート作家は貧困の状況に陥りやすいのか。このあたりの分析は驚きがたくさんあった。5章と12章の内容が合うならスムーズに読み進められるように思う。英語が問題ない方なら、PDFが公開されてるのでそちらを読むのがおすすめ。2021/05/19
ばるさん
1
興味深くはあるがあまりピンと来ないのは主に欧米主体の話だからだろうか。日本と比較して共通点や差異を考える点では面白い。助成金の観点では芸術への公的支援はそれほど多くないように思うし、昨今は特にローアート分野の興隆が甚だしいのでハイアートはかなり割を食わされているのではと。アーティスト志向についてはまさしくその通りで、自分は小説家なんかに当てはめて考えてみて興味深く読めました。2013/01/31
-
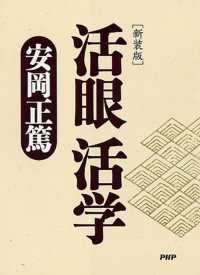
- 和書
- 活眼活学 (新装版)