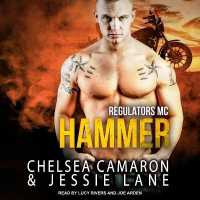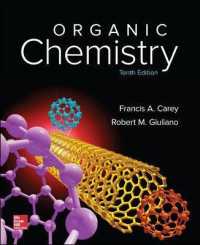内容説明
貧困問題の解決に鋭く切り込む世界的名著。ピューリッツァー賞など13の賞を受賞。TIME誌「2010年代ノンフィクションベスト10」選出。
目次
プロローグ 凍える街
1 入居(町を所有する商売;大家の悩み;湯の出るシャワー;みごとな回収;一三番ストリート;ネズミの穴;禁断症状;四〇〇号室のクリスマス)
2 退去(どうぞご用命を;雑用にむらがるジャンキー;スラムはおいしい;“その場かぎり”のつながり;「E-24」で;がまん強い人たち;迷惑行為;雪の上に積もる灰)
3 それから(これがアメリカよ;フードスタンプでロブスターを;小さきもの;だれもノースサイドには住みたがらない;頭の大きな赤ん坊;ママがお仕置きを受けることになったら;セレニティ・クラブ;なにをやってもダメ)
エピローグ 家があるからこそ、人は
著者等紹介
デスモンド,マシュー[デスモンド,マシュー] [Desmond,Matthew]
プリンストン大学社会学教授。2010年、ウィスコンシン大学マディソン校で博士号を取得後、ハーバード大学のエリート研究者養成制度であるソサエティ・オブ・フェローズのジュニア・フェローに選ばれる。「天才賞」として知られるマッカーサー・フェローシップにも選出され、アメリカ法曹協会のシルバー・ギャベル賞、ウィリアム・ジュリアス・ウィルソン・アーリー・キャリア賞も受賞した。The Eviction Lab(強制退去研究所)の主任研究員でもあり、アメリカにおける貧困、都市生活、住宅問題、人種間の格差などに果敢に取り組み続けている
栗木さつき[クリキサツキ]
翻訳家。慶應義塾大学経済学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヘラジカ
泰然
サトシ@朝練ファイト
キクチカ いいわけなんぞ、ござんせん
Mc6ρ助