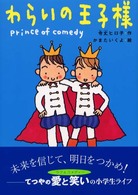感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
28
(p.148)本質的なのは、語ることであり、きみの手が、今この世を去ろうとしている人の手にさし伸ばされ、きみの目の光が、もう何も見るものがないところに向けられている他者の目と出会うこと、他者の息が絶えるときに、きみの声の暖かさが、その人のところに届くことなのである。2022/08/25
かふ
25
プラトン・アリストテレスから始まる合理的な知の共同体がある一方で西欧社会からは見えない未開とされる共同体があり、その中でも死を賭した自分自身の身体以外に持たざる得ない共同体(パレスチナ)のような世界があり、西欧の合理主義の体系からは説明できない知(野蛮とされる)の体系があるという脱構築の哲学なのか。メルロ=ポンティの現象学からレビナスの根源性を経てフーコーの構造主義に至る感じか?死を介して共同体はブランショやジャン=リュック・ナンシーを踏まえているような。2024/12/29
吟遊
10
リンギスの本領が垣間見える。ノイズの世界に耳を傾け、いや、体を浸し、あらゆる人間以外のものの声を享受し、喜びを覚え、そしてその感覚は死につながる、とリンギスは言う。2019/08/15
Sakana
7
読書ノートを書くために再読。合理性に回収されてしまうもの、そのプロセスの中で取捨されてしまうもの、そこで零れ落ちる様々な事柄を拾い上げようとする試み。それは例えば、コード化された言語という合理的なプログラムだけでは伝わらない、表情や仕草、リズム、まわりの雑音、涙声や叫び…だったりする。「生きるということは、物がだす振動に共鳴するということなのである」というリンギス。「生きていること」、「死ぬこと」、そして「他者とは」を、本源的に、そしてラディカルに問うてくる。でも読んでいて心地いい、とても優しい本だった2018/05/03
薫風
6
現象論の優れた思想家アルフォンソ・リンギスの著作。我々が社会で使用する言語というものは、ある種の共通的な思想・価値観に基づいて発言されるからこそ、合理的な発言として受け入れられる。しかし、この世界には、この共有された思想・価値観を逸脱する存在や瞬間というものがあり、その筆頭が、”死”というどこまでも個人的で共有し得ない現象である。この共有という概念をもとに世界を再解釈する、自分にとっては新鮮な視点をもたらす一冊でした。2025/06/15
-
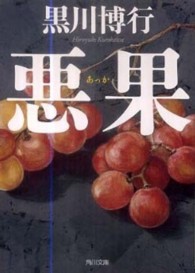
- 和書
- 悪果 角川文庫