内容説明
社会は、変えられる。問題には、対処することができる。そう信じて動くこと、答えはそこにしかありません。日本の教育、仕事、そして若者。いったい何が問題なのか?教育社会学者・本田由紀が、日本の進むべき道を考える。
目次
1 日本の教育は生き返ることができるのか
2 超能力主義に抗う
3 働くことの意味
4 軋む社会に生きる
5 排除される若者たち
6 時流を読む―家族、文学、ナショナリズムをキーワードにして
7 絶望から希望へ
著者等紹介
本田由紀[ホンダユキ]
1964年生まれ。東京大学大学院教育学研究科准教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程を単位取得退学。博士(教育学)。日本労働研究機構研究員、東京大学社会科学研究所助教授を経て現職。専門は、教育社会学。著書に『多元化する「能力」と日本社会』(NTT出版、第6回大佛次郎論壇賞奨励賞を受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん
4
個人的には、数値を出して格差を実証することにあまり意味はないと思います。かならず、それは格差ではなく、正当な評価であり、無能で怠惰な人間のたわごとだという人がいるから。そういう意味で、金持ちは人の家族に安い労働力の保持を押し付け、社会の安定のためのコストから逃れている、とする、「正しさ」を競り取るための武器が紹介されているのが、本書の魅力でした。自分の無能と怠惰を当然な権利として正当化するための権力争いこそ問題の本質で、その闘争にちゃんと参加できるかが、格差問題の解決には重要な意味を持つのだと思うのです。2021/10/16
じょに
3
p.79にワーキング・プアの人達に対して「だから何?って感じですかね」と言う若者が出てくる。自分も似たような発言に出くわして随分ショックだった経験があるのを思い出した。大方はそう考えているのだろう。誰だって自分は失敗したくないだけだ。でも見たくないものを見ないことは倫理的でないと思う。でも残念ながらこの本に書いてあることは「仕方ない」で片付けられてしまうんだろうとも思ってしまう。問題はもう一層より根深い気がする。2009/04/25
Jagrass03
2
より正確に若者の雇用実態を捉えて、更に解決策をも提示する頼もしい書。やや値は張るが、雇用に関して何らかの問題意識を抱いているなら読むべき本だと思う。2010/05/14
MADAKI
1
【日本型社会モデルの終焉】東大で教育社会学を研究する本田教授による社会論。筆者の拠る社会のストーリーは明瞭で、戦後の経済成長期に確立されてきた、良い高校、大学→良い会社→会社は社員の滅私奉公の代わりに家族ぐるみで生活保障→働くパパ、専業主婦、子供の核家族→子供が学歴社会に参入…というサイクルが現状崩壊(あるいは、軋み)を迎えているというものだ。経済的理由から会社が社員を守れなくなり、結果やりがいの搾取のような不均衡が起こる。社会に柔軟さを取り戻すべきという筆者の主張は、今でも説得力を失っていない。2012/09/01
おじ
1
西きょうじ先生の講演で知った本。「コミュ力」「人間力」といった言葉に疑問を持った人は必読。よくわからん言葉に振り回される若者達のこれまでとこれから。子どもから大人までお勧め。2014/12/22
-

- 電子書籍
- 真・上京シェアハウス~彼女と幼馴染と知…
-
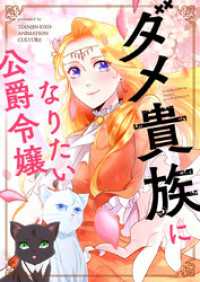
- 電子書籍
- ダメ貴族になりたい公爵令嬢【タテヨミ】…
-

- 電子書籍
- 「ODA」再考 PHP新書
-

- 電子書籍
- らんま1/2〔新装版〕(4) 少年サン…
-
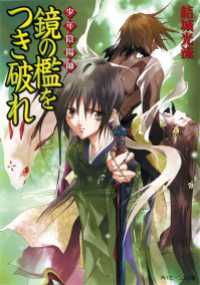
- 電子書籍
- 少年陰陽師 鏡の檻をつき破れ 角川ビー…




