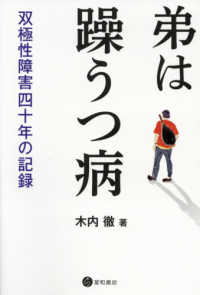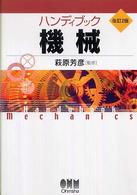目次
日本社会がかかえる問題とおとな
成熟と共生をめざすおとなの学び
おとなの学びの語られ方―生涯学習
おとなが学ぶとは1―経験の尊重と問題の設定
おとなが学ぶとは2―省察的実践
おとなが学ぶとは3―意識変容の学習
学び合いを創造する
高等教育機関での学び合い
教師の学び合い
看護専門職の学び合い
企業での学び合い
地域での学び合いと学校
江戸時代の学び合いの循環型社会
著者等紹介
三輪建二[ミワケンジ]
1956年生まれ。東京大学法学部私法コース、同大学院教育学研究科博士課程修了。教育学博士。東海大学、上智大学、お茶の水女子大学、日本教育大学院大学を経て、星槎大学大学院教育実践研究科教授。専門は成人教育論、生涯学習論、省察的学習論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
28
自我形成のための子どもの学びと異なり、おとなはすでに持つ経験を踏まえて学ぶ。ともすると邪魔者扱いされかねないその経験を、ここでは逆に貴重な学びの資源として尊重する。同時におとなの学びの姿として注目するのがショーン「省察的学習」とクラントン「意識変容の学習」。仕事をはじめ活動しながらの学びは、学習→省察→実践→学習とぐるぐる往還。それにより、情報を得るだけではなく自己の変容が起こる。学び合いや共生はそうやってすすむ。◇ここでは競争のためと否定的に語られがちだが、資格や仕事の学習も、豊かな学習の大切な源泉だ。2018/12/24
ひよこ
1
学び直しをしながらこの本を再読したい。コラムでは書籍の紹介をしていておもしろい。2024/01/28
テト
1
資格を目指して学ぶ学び方もあるのだけれど、個人ではなく共同体のなかでどのように生きていくのか、ということも大切なことと感じた。問題を設定して、学びあ合いのなかから省察、意識変容から、他利と共生を目指すことがおとなの学びで大切なことと学んだ。2021/07/14