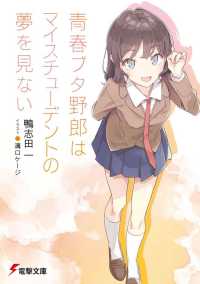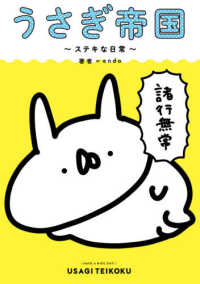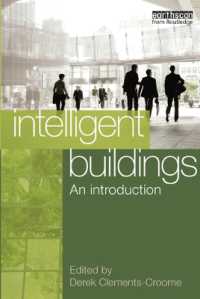内容説明
「日本に天皇制って必要だよね」と思う、その「あたりまえ」をひっくりかえす。
目次
「あたりまえ」だとおもっていることは、ほんとうに、あたりまえなのかしら?
あなたは天皇を尊敬していますか?
あなたは徳仁さんが好きですか?
どうしてもわからないことがあります
象徴天皇制ってアメリカ製なの?
これは、わたしたちのいまの生きかたへの罰ではないのか?
あなたは「国」を愛せますか?
なぜ、死を意義づけようとするのでしょう?
明仁天皇は、サイパン島で、なにをしたのでしょう?
明仁さんのパフォーマンスは、なにを意味していたのでしょう?―天皇のパラオ「慰霊」の旅について〔ほか〕
著者等紹介
彦坂諦[ヒコサカタイ]
1933年、仙台で生れ、山口で育つ。1945年、父の転勤に伴い「大日本帝国」の植民地都市「旅順」に移り、ここで敗戦を迎え、まもなく難民として大連に追放された。1949年、中国・大連より「引揚者」として帰国。東北大学で日本史を、早稲田大学大学院でロシア文学を学んだ。木材検収員などのアルバイトで生計を維持しながら、1978年より1995年まで、約17年の歳月をかけて、シリーズ「ある無能兵士の軌跡」を完成させた(全9巻、柘植書房新社、第一部『ひとはどのようにして兵となるのか』上下、第二部『兵はどのようにして殺されるのか』上下、第二部別巻『飢島1984←→1942』、第二部別冊『年表ガダルカナル1942.10/1-27』、第三部『ひとはどのようにして生きるのびるのか』上下、第三部別巻『総年表・ある無能兵士の軌跡』)。同シリーズは、わたしたちの日常に潜む戦争の根を、わたしたち自身が内在化している能力信仰、集団同調、異分子排撃などの問題として追究。また、その過程で書かれた『男性神話』(径書房)は「軍隊慰安婦」問題に対する男性の側からの真摯な発言として注目された〃(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
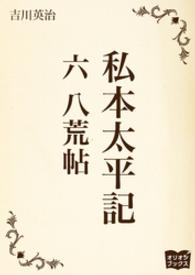
- 電子書籍
- 私本太平記 六 八荒帖