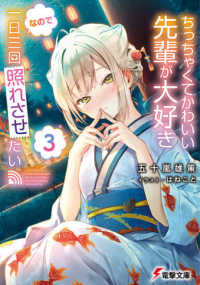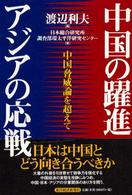内容説明
いじめ、不登校、引きこもり、その原因は何だろう?学校、教育のあり方を根本から問いただす。気づきのシリーズ第4弾!「お金」を通して考える生き方論。
著者等紹介
長島龍人[ナガシマリュウジン]
1958年、東京生まれ。武蔵野美術大学卒業後、広告代理店入社。2003年、「お金のいらない国」出版。以後、寸劇に仕立てたものを自ら演じたり、自作の歌を歌ったりと、理想社会のイメージを伝えるため、さまざまな活動を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
izw
8
「お金のいらない国」シリーズ第4巻。学校・教育も、お金のいらない国では、根本的な考え方が異なる。働かずに遊んで暮らすこともできて、いい学校を出て、資格を得て、職につく必要がないので、好きな時に、好きな勉強をして、そのとき必要なことを学べばよい。これ自体は納得できる考え方だ。あとは、人間にはある年齢まで修得すべき(しておくとよい)能力があるので、それを逃さないようにするだけだが、それが共通認識にさえなっていれば何とでもなるかもしれない。最後にサッカーの描写があるが、勝敗がないとルールそのものが異なるかな。2021/10/23
ブック
3
シリーズ第4作では、第3作同様に例の紳士がこちらの世界を訪れるのだが、今回は幽体離脱状態で登場する。双方の世界のあちこちを自由に移動しながら、わかりやすくこの世界の矛盾を指摘していく。いちばんのメッセージは「受け止める」というスキルだろう。我々は意見のちがう他者と対立し、相手を否定するが、この感情がなぜ起こるのかを見つめ直すと、やはりそこには「余裕のなさ」があり、そこにお金の存在が浮かび上がる。他者を受け止めることは、誰にでもできる。但し努力が必要だ。私もその努力をしなければと痛感させられた。2022/12/26
山口 公大
1
「ティーチングとコーチングの違い」、「受け止めると受け入れるの違い」、「教育と学びの違い」、「◯×教育の弊害」、「腹は立たない、立てているだけ」と言うような様々な歪な当たり前にわかりやすく気づかせてくれる。 2020/08/23
らま+たん
1
「お金のいらない国」は1、3、4作目の3冊を読んだけどこれが一番共感度が低かった。シリーズを通して伝えてくれる『自分の在り方次第でヒトは如何様にでも成れる』的なメッセージ部分は変わらず共感できる。しかし、シリーズを通して言う「お金のない国での社会生活」を実現しようと思ったら自由度が高過ぎるゆえ、自分だったら時間が足りなくなる弊害が生じるだろうな、と感じた。今ある社会がすべて悪いわけではなく、いいところは残しつつ、お金のない国の良いエッセンスを取り込めたら素敵な事だと思う。2017/02/05 07:532017/02/05
めぐみ
0
なぜ争いが起きるのか考えるきっかけになる本。 なぜ喧嘩になるのか、戦争になるのかなど、揉める原因について考えさせられました。 始めは些細なことでも、人は自分のため、必要以上を求めることが原因で起こることが多く、それぞれの考えるが伝わらないからそれが悪化するのかもしれない。 余裕をもって真剣に信頼して何事にも向き合えば答えは出てすることも分かることを教えてもらった気がします。 平和を願う人、幸せを願う人、それぞれが自分らしく生きることを望む人にオススメな本です。2017/10/23