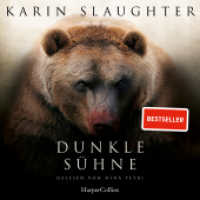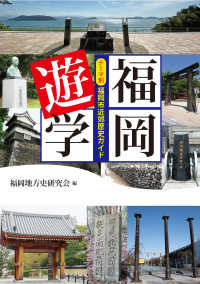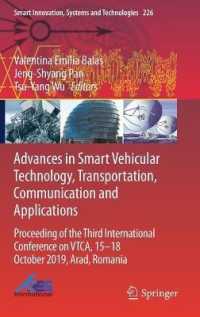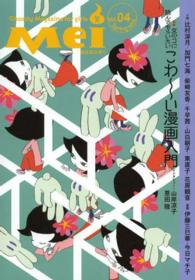内容説明
構造構成主義に脳科学や認知科学の成果を援用し、「ひとで成り立つ医療の源の視点」をひも解く。
目次
1 問題の所在―緩和ケアの特徴と関連し本質的に内在する問題について(「辛さ」に焦点を当て、これに対応する―主観を治す;全人的医療を志向する―意味や価値をも対象とする ほか)
2 構造構成主義について(構造構成主義とは何か;構造構成主義が持つ関心 ほか)
3 重要な概念について(主客問題・認識問題;自然的態度 ほか)
4 臨床に直結する7つの具体例(「痛み」について;「せん妄」について ほか)
著者等紹介
岡本拓也[オカモトタクヤ]
1966年、兵庫県淡路島に生まれる。兵庫県立洲本高校、京都大学法学部卒業後、浪速少年院法務教官、キリスト教会奉仕を経て、北海道大学医学部を卒業し医師に。札幌医科大学地域医療総合医学講座からスタートし、聖隷三方原病院、栄光病院での勤務を経て、現在は洞爺温泉病院ホスピス長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Soshi Mori
1
うん、とても面白かった。自分は全く緩和ケアには関わっていないが、それでも自分の志向性にとってはとってもぴったりな内容でした。特に後半の「痛み」や「せん妄」などをテーマにした具体例の部分に関しては、それらを構造構成的に著していて他にはあまりない感じではないかと思います。タイトル通り全体を通してわかりやすかったです。2015/06/07
ソーシャ
1
緩和ケアに構造構成主義の考えを取り入れようとしている著者による分かりやすい構造構成主義の入門書。臨床家が応用することに重点が置かれていて、信念対立を解きほぐす方法論について分かりやすく簡潔に解説されています。構造構成主義の考えをざっとつかむにはいい本ですね。2014/07/25
はしはし
1
緩和ケアとは何か?を普段とはちょっと違う側面から捉えて見るには良い本でした。日頃緩和ケアに関わりながらも悶々としている事柄を考える一つのヒントに。2014/04/26
yuka_tetsuya
1
現実と認識とは異なるが故に、認識は多様であり、正解はない。我々の思考の基軸となっている言語は世界を切り取って表現したものであり、抽象的な事柄には曖昧さがともなう。緩和ケアは全人医療の最たるものであり、生きる意味や痛みと言った抽象的な事柄を扱う。多職種のチームが患者および家族の複数の認識と向き合うとき、認識の対立が起こることは当然である。この多対多のこんがらがったヒモをほどく方法として構造構成理論がわかりやすく紹介されている。「相対化」「判断中止」「還元」「戦略的ニヒリズム」など大変に勉強になった。2013/04/21
OHモリ
0
●少年院法務官の経験を経て緩和ケア医になった岡本先生がスピリチュアルケアではなくて哲学の本? ●「ナニコレ・・」の阿部先生とは同じ緩和ケア医だけどまた違った切り口からで構造構成理論の理解が深まる。 んが、内容もよくわかって共感できるし勉強にはなるけど、正直なところ「目の前にある本やリンゴが本当に存在するのか?」というところまで原点にさかのぼる必要があるの?とも思う。 ●考え方はわかったけど、あとは経験に基づいた具体的で実践的なことになるわけだけど、考え方と実践のギャップが大きいと感じますが良書です。 2016/10/30