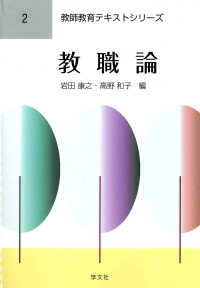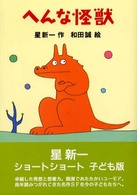内容説明
あくまで誠実に、そしてあくまで貪欲に。時代の言葉と共に生き時代の言葉との戦いに挑んだ谷崎潤一郎。その思想家としての可能性を切り拓く。
目次
序章 “芸術”の危機?―谷崎潤一郎と/の一九二〇年代
第1章 一九二〇年、映画・谷崎・群衆―『アマチュア倶楽部』再評価に向けて
第2章 アメリカという名の幻影―“近未来小説”としての『痴人の愛』
第3章 差異と消費とニヒリズム―『卍』、あるいはブルジョアたちの憂鬱な祝祭
第4章 喪失とひきかえに―『蓼喰ふ虫』と“回帰”する男たち
第5章 小説としての闘争/小説からの逃走―『吉野葛』、谷崎潤一郎・一九三一
著者等紹介
五味渕典嗣[ゴミブチノリツグ]
1973年、栃木県生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科国文学専攻博士課程修了。博士(文学)。中央大学附属高等学校教諭を経て、大妻女子大学文学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あなた
7
五味渕さんの論考をゆっくりと読み直しているのだが、彼の醍醐味は次のように要約されるように思う。精緻なテクスト分析。そしてそれを短絡的かつ安易に同時代言説に結び付けていくわけではなく、同時代言説の構造を症候的に析出しつつ、テクストと同時代言説をどちらかに与するかたちでは・ないかたちで連絡し、関連付けていくこと。それはひいて「文学」、あるいは「文学系」さらにいえば「文学研究という問題圏域」の脱臼に他ならない。また彼は縦横無尽に思想家たちを召喚する。(コメントに続く2010/07/27
あなた
7
五味渕さんの論文を読んでいるとその問題系にとどまらず、必ず、ことばを通し、ことばに通されて生き・生かされてあるこの〈わたし〉とは〈なにもの〉である/ないのかという根源的な問題圏までたどりつく。発話された〈ことば〉を自己参照しつつ自己言及していく試みが文学であるならば論文にもそういった文学性があることを本書を読んでいるとふいに感じたりする2010/05/17
あなた
6
五味渕さんは論文タイトルがいつも素敵で文体も独特でしたが(どこかヒロイックでロマンチックでもあった)、〈言葉を食べる〉ってまたいいタイトルつけますね。松本和也さんの太宰関係の本もたくさん出版され、藤井貴志さんの芥川の本も出て去年から今年にかけて若手研究者のエポックを感じます。早稲田の地下でこそこそ彼らの論文コピーしたなあ。あと慶應の地下書庫で五味渕さんの博士論文こそこそ読んだりとかしてたなあ。幸福だった2010/04/30