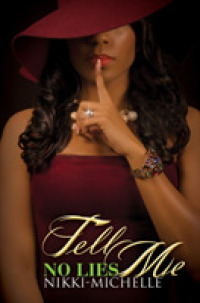目次
考古学今昔物語第一話「20世紀の考古学、21世紀の考古学」(基調講演「20世紀の考古学、21世紀の考古学」(考古学を志した頃;考古学の黎明期 ほか)
座談会「20世紀の考古学、21世紀の考古学」(モノと考古学;発掘調査の手引き ほか))
考古学今昔物語第二話「考古ボーイズ70年」(基調講演「考古ボーイズ70年」(卑弥呼の時代の刀;縄文時代から弥生時代への移り変わり ほか)
座談会「考古ボーイズ70年」(考古ボーイの面々;考古学を志す ほか))
「考古学今昔物語」余話(むきばんだやよい塾;佐原先生の入院 ほか)
著者等紹介
坪井清足[ツボイキヨタリ]
1921年、大阪に生まれる。父良平は梵鐘研究家。34年、大倉商業学校に入学。このころ父や小林行雄、藤森栄一について各地の遺跡を回る。41年、京都帝大に入学。43年、召集。44年、台湾に上陸。終戦直前、鳳鼻頭遺跡陣地トレンチ等より遺物採集調査。46年、復員。大学に復学して滋賀里遺跡等の発掘に参加。49年、京都大学大学院に在籍。50年、平安中学・高校に就職。55年、奈良国立文化財研究所に入所。67年、文化財保護委員会記念物課文化財調査官を併任。75年、文化庁文化財保護部文化財監査官。77年、奈良国立文化財研究所長。86年、同退官。同年、財団法人大阪文化財センター(95年から財団法人大阪府文化財調査研究センター)理事長。2000年、財団法人元興寺文化財研究所副理事長。83年度第35回NHK放送文化賞を受賞。90年度大阪文化賞を受賞。91年度朝日賞を受賞。同年、勲三等旭日中綬章を受賞。99年、文化功労者
金関恕[カナセキヒロシ]
1927年、京都市生まれ。父は医学博士(解剖学)で、考古学者としても有名な金関丈夫。36年、その父の仕事の関係で台北に転居。父親の発掘調査を手伝う内に、考古学の面白さに魅了される。53年、京都大学文学部史学科考古学専攻を卒業。同大学院を経て、56~59年、奈良国立文化財研究所臨時筆生。その間、山口県土井ヶ浜遺跡、梶栗浜遺跡など弥生時代の遺跡や、奈良飛鳥寺跡、大阪市四天王寺跡など最古の仏教寺院の遺跡調査に参加。59~96年、天理大学に勤務。同大文学部教授。日本オリエント学会主催のイスラエル、テル・ゼロール遺跡の発掘調査に参加。その後「聖書考古学発掘調査団」を組織して、エン・ゲブ遺跡の発掘を継続。91年以降、大阪府立弥生文化博物館館長
佐原真[サハラマコト]
1932年、大阪市に生まれる。幼稚園時代、豊中市の青池の須恵器の窯跡で土器片を拾い、考古学に興味を持つ。43年、東京に転居。53年、大阪外国語大学ドイツ語学科に入学。58年、京都大学院修士課程に入学。64年、奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部に入る。73年、飛鳥資料館勤務。81年、奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センターの研究指導部長を経て、92年には同センター長に就任。93年には、国立歴史民俗博物館企画調整官(副館長)、97年には同館長に就任。2001年、同館長を退任し、名誉教授になる。02年7月10日、永眠
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 洋書
- The Works