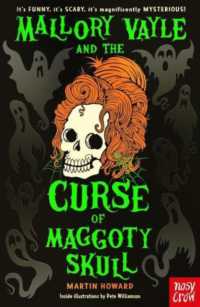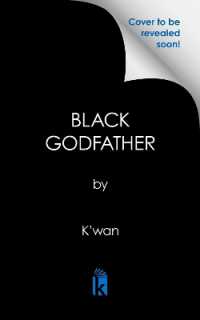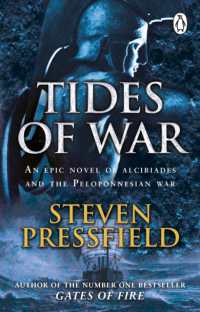内容説明
テクストと向きあう“読むこと”の透徹した営みによって、現代における批評の新たな方向性を決定づけた古典。ブランショ、プーレ、デリダらと果敢に対峙し、彼らの洞察そのものが不可避的な内的齟齬への盲目性によって支えられていることを暴く。鋭利な考察が今なお輝きを放つ、イェール学派の領袖の主著。
目次
第1章 批評と危機
第2章 アメリカのニュークリティシズムにおける形式と意図
第3章 ルートヴィヒ・ビンスヴァンガーと自己の昇華
第4章 ジェルジ・ルカーチの『小説の理論』
第5章 モーリス・ブランショの批評における非人称性
第6章 起源としての文学的自己―ジョルジュ・プーレの著作について
第7章 盲目性の修辞学―ジャック・デリダのルソー読解
第8章 文学史と文学のモダニティ
第9章 抒情詩とモダニティ
著者等紹介
ド・マン,ポール[ドマン,ポール][De Man,Paul]
1919年ベルギー・アントワープ生まれ。ブリュッセル自由大学で工学、後に化学を専攻し、哲学や文学も広く学ぶ。1948年合衆国に移住。1960年ハーヴァード大学にてPh.D.取得(比較文学)。コーネル大学、ジョンズ・ホプキンズ大学、チューリッヒ大学などで教鞭を執り、1970年以降、イェール大学比較文学科教授。1983年没
宮崎裕助[ミヤザキユウスケ]
1974年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程(表象文化論)修了。博士(学術)。専門は哲学、現代思想。現在、新潟大学人文学部准教授
木内久美子[キウチクミコ]
1978年生まれ。イギリス・サセックス大学人文学部英文学科博士課程修了。D.Phil(英文学)。専門は比較文学、イギリス・アイルランド演劇、翻訳論、ジャンル論。現在、東京工業大学外国語研究教育センター准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
SHIGEO HAYASHI
ミスター
aabbkon
太陽
-
- 洋書
- Tides of War