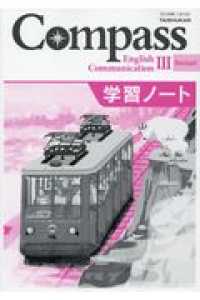出版社内容情報
ムラの診療所で、アジアの辺境で、ヨーロッパの街角で……。地域医療に携わる医師が出会った人々と命の姿をめぐって考えたこと。朝日新聞長野版連載「風のひと・土のひと」が待望の単行本化。地域から日本が変わる!
金持ちより心持ち──まえがきに代えて●色平哲郎
下のお世話──人のつながり、わかる瞬間
家族旅行──院内から船内、ゾウの背中
習い事と試験──ノートとは……むむっ卑怯な
消えゆくムラ──日々圧倒される知恵と技
投票に行こう──山のムラも国際社会に直結
ふるさと──川の流れに結ばれて
医者どろぼう──金を介さぬ時代の治療費
介護の社会化──時代に揺らぐモンダ主義
シンシアの診療所──「難民」たちとの出会いと別れ
「支え合い」の介護──現実知らぬ「家族で」の論調
ムラの老人たち──大地に根を張る知恵と技
道普請──今も生きる自治の伝統
五輪効果──巨大開発と国際化の模索
川のふるさと──新世紀へ水の贈りもの
野性の老人──地域に根をおろす偉大さ
山下将軍の亡霊──韓国人愛国者の複雑な胸中
地雷と眼科医──平和をねじれさせる「構図」
沈黙の証言──時代、ひざや腰に刻まれて
看取るということ──隣人として背景見つめる
老い方の作法──ムラビト縛る都市の「網」
ムラ医者の誕生──放浪で出あった互助の心
来世紀の農業像──厳しい現状と食糧安全保障
歴史の追体験──複雑な民族感エネルギーに
ベニスの商人──富の再生産、利子と世襲
転がる力──人馬車……輸送に隔世の感
乳幼児の誤飲──日本の生活習慣に必然性
百俵のコメ──水と空気と日光に支えられ
「政治」の本質──平等に負う合意形成の技術
「国際化」──かけ声にかすむ文化的差異
夏は来ぬ──「厚塗り」国土の熱中症
強者の言葉──人間扱いされるために
「心の病」──向き合い受けとめる
痛みを伴う改革──「治療」するのはだれ?
ご 縁──巡り巡ってつながる心
美しい国土──里山の景観に人癒す力
水の循環──森と田は「みどりのダム」
国民皆保険──すばらしい制度の存続を
親不孝の系譜──選び取る「自分の生き方」
老後の心配──市場の緩和だけでは……
医療行政の使命──リーダーの方針明示が重要
地域通貨──よいつながり構築に有効
旅──東洋人であること学ぶ
感じる力と覚える力──周囲から学ぶ姿勢が大切
リテラシー意識──自己の埋没防ぐ「批判の目」
語り合える友──私自身の内面映す「鏡」
子 縁──学校を地域の基地に
百人の村──広い視野と低い視点を
本物の勇気──すべてさらけ出し生きる事
(金持ちより心持ち──まえがきに代えて●色平哲郎)より
この「金持ちより心持ちになろう」というモットーは、もちろん、私に金持ちになる気力と能力がほとんど無いことを前提に、やっかみで言っているのである。そして心貧しい私であるからこそ、周囲の心豊かな人々にあこがれる思いで、「心持ち」に、もしなれるとすれば、それはお金の関係ではない友人をたくさん持っていることなのではないか、と強弁しているのである。
山の村の医師住宅、居間にある金魚鉢の中で、金魚はクルクルと泳いでいる。なぜも、こんなに楽しそうなのだろう? クルクルまわり続けるしかない、とも言えようが、しかしうれしそうに見えている。金魚の脳は、三十秒間しか記憶力が保たないので、周囲の景色が毎周毎周いつも新鮮に映って、ウキウキしているのだ。そう聞いたことがあるが、本当だろうか?
戦後の日本は、カネ・キカイ・クルマ・ケイタイ・コンビニの「カキクケコ」に代表される豊さの拡大を目指し努力を結集した。小さかった金魚鉢はどんどん大きくなって、目新しいウキウキ刺激が人々の心を捉えた。
戦後の社会変化は、高度経済成長に代表されるように「個人」より「組織」ピン民衆のことわざも想い出した。
一方、村人と話していて、今への戸惑いを伺うことがある。
「学問もねえからようわからんだども…… おまんま食って、いつでも食べたいときに食べられる。 こごとがなくて、うちじゅうにけんかがなく、気楽だ。 いえでよく寝て、あんどに暮らせる」 ――「幸せなんだね」―― 「(今が)あんまり幸せすぎて、いったいどういうことだ、と考えてしまう……」。
それにしても、教育だ、勉強だ、学習だ、とはいっても、私の大きな不安と不満は、現状が「教えられたことをただ覚えるだけ、そして正解を早急に求めすぎる」点にある。逆に、「ちがい」と「まちがい」を大切にできるような教育観こそ大事なのではないか 。実に「ちがい」と「まちがい」が許されるような学校空間が今こそ求められている。寛容な雰囲気は日本社会全体で渇望されていると感じる。
「人はみんなそれぞれ『ちがい』ます。それでおかしくないし、世界は多様で、多民族で多宗教で当たり前だし、それを押し出しても決していじめられたりしない、ちがっていることこそ二十一世紀には価値になる……。『まちがい』もそうです。誰も決してまちがえたいと思って取組むわけで」といっています。
おもしろいです。
おとうさんは、あたまのまんなかがはげています。
おとうさんは、ごろうがいると「ごろごろごっこ」をしてあそんでくれます。
おとうさんがわるさをすると、うちのかぞくはすごくおこります。
おとうさんは、わたしたちがたべてるものをよこどりをします。
わたしは、おとうさんのことがすきでもきらいでもありません。
ごろうは、小さいときに、おとうさんのことを「ブー」といっていました。
わたしは、小さいときに、「さる」といいました。
おにいちゃんの小さいときは、「バイキンマン」と、いっていました。
ついでに、テレビの感想文も書いてもらった。
テレビで見たことを書きます。
テレビで赤ちゃんがうまれるところを見ました。
わたしはおもいました。
赤ちゃんをうんでいる人もがんばっていました。
赤ちゃんもがんばっているとおもいました。
おいしゃんさんも、がんばっていました。
わたしもこうやってうまれてきたとおもいました。
本書は、二〇〇〇年五月十一日から二〇〇一年十二月二十日まで、朝日新聞・長野県版に「風のひと 土のひと」というタイトルで、週一回連載
念ずれば花開くこともある、のが出版という稼業の面白さ。不思議なことに朝日新聞の連載が始まってからずっと気になっていたが、本になるときは、きっと自分が手がけることになる筈だ、とも思っていた。色平さんは強烈にして確固たる理念を持っている人であり、それを実践している希有な医師でもある。その著者のもつ理念への共鳴とシンパシーが、今回の発刊に繋がったと信じている。同時に森貘郎氏の板画(ばんが)が、後押ししてくれてもいたことも事実である。こんな出会いができるのも、この稼業にたずさわっていればこそ。
内容説明
ムラの診療所で、アジアの辺境で、ヨーロッパの街角で…地域医療に携わる医師が出会った人々と命の姿をめぐって考えたコト。「朝日新聞」話題のエッセイ「風のひと 土のひと」が1冊に。
目次
下のお世話―人のつながり、わかる瞬間
家族旅行―院内から船内、ゾウの背中
習い事と試験―ノートとは…むむっ卑怯な
消えゆくムラ―日々圧倒される知恵と技
投票に行こう―山のムラも国際社会に直結
ふるさと―川の流れに結ばれて
医者どろぼう―金を介さぬ時代の治療費
介護の社会化―時代に揺らぐモンダ主義
シンシアの診療所―「難民」たちとの出会いと別れ
「支え合い」の介護―現実知らぬ「家族で」の論調〔ほか〕
著者等紹介
色平哲郎[イロヒラテツロウ]
長野県南佐久郡南相木(みなみあいき)村診療所長、内科医、NPO「佐久地域国際連帯市民の会(アイザック)」事務局長。1960年神奈川県横浜市生まれ、42歳。東京大学中退後、世界を放浪し、医師を目指し京都大学医学部へ入学。90年同大学卒業後長野県厚生連佐久総合病院、京都大学付属病院などを経て長野県南佐久郡南牧(みなみまき)村野辺山へき地診療所長。98年より南相木村の初代診療所長となる。外国人HIV感染者・発症者への「医職住」の生活支援、帰国支援を行うNPO「アイザック」の事務局長としても活動を続ける。こうした活動により95年、タイ政府より表彰を受ける。現在、長野県東南部、人口1300人の南相木村で家族5人で暮らしている
森貘郎[モリバクロウ]
板画家・杏の里板画館主宰・日本板画院同人。1942年、長野県更埴市生まれ。棟方志功の「板画思想」に共鳴し、自らも板画(ばんが)と呼び、制作を行う。郷土の民話やわらべ歌、また小林一茶や山頭火の俳句を主題にするなど、詩情豊かな作品を発表。古い民家を保存再生した「杏の里板画館」設立や文化財保存運動に取り組むなど、地域に根ざした独自の創作活動を続けている。1980年より毎年「一茶暦」を制作
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書
- Tattine