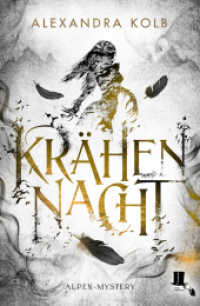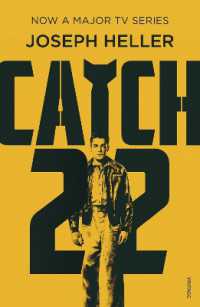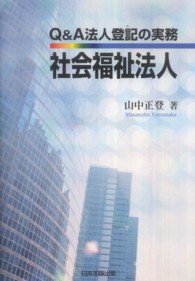内容説明
世界の目を、日本の霊長類学に向けさせた発見の数々。半世紀以上に及ぶ研究生活からいま明かす、研究とはなにか、またその「成功」と「失敗」とは。
目次
第1章 霊長類学の故郷・高崎山(高崎山のサルの歴史;群れ分裂の発見;増えすぎたサル山のサル;個体群の管理を試みる;出産率を抑える;森林破壊の実態;これからの高崎山)
第2章 普通か例外か―霊仙山のサル(頻繁な雄の出入り;群れを離れる雌;雌の群れ離脱は例外か;なぜ雌が群れから離れるのか;優劣順位と子孫残し率;優劣と順位序列に関する認識の差;群れの輪郭)
第3章 神の使い―子殺しをするハヌマン・ラングール(集中調査地点を絞る;社会構造と種内子殺し;子殺し発見を世界に発信;一転した欧米の反応;国内ではほとんど無反応;子殺しはハヌマン・ラングール共有の特徴か;子殺し発見の果たした役割;なぜ私であり、私でなかったのか;広まりのメカニズム;その後の進展)
第4章 動物としてのチンパンジー―東アフリカから西アフリカへ(ブドンゴの森の離合集散;ボッソウの社会集団と繁殖集団;分散と移籍の構造;成長、成熟、そして老化;流行病によってもたらされた個体数減少;独自の文化;工具を操るチンパンジ0?;房づくりの真相)
第5章 大学教育への参加(いかに調査へのお返しをするか;ギニアの大学の現状;堕医学とその設備;教育参加のきっかけと準備;いざ、授業開始;学生たちの質問;二年目の授業を効果;これからの教育参加をどう進めるか;あらためて現地貢献について考える)
著者等紹介
杉山幸丸[スギヤマユキマル]
1935年旧満州新京生まれ。1963年京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。京都大学理学部助手、霊長類研究所助教授を経て教授。1996年より所長。1999年退官。2000年より東海学園大学教授。2004年まで人文学部長。2006年退職。日本霊長類学会会長、日本生態学会中部地区会長、ギニア共和国高等教育科学研究省招聘教授を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。