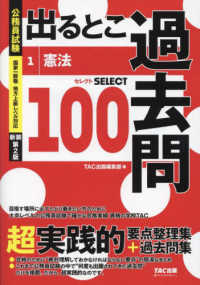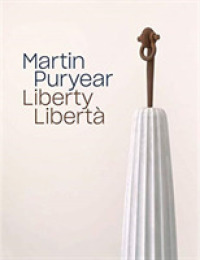内容説明
歌人にして社会学者による短歌・俳句の分析。五・七・五+七・七の世界を社会学が分析する。
目次
1部 短歌・俳句論(短歌・俳句比較研究ノート;戦争を短歌・俳句はどのように詠めるのか―戦後の朝日歌壇・俳壇を対象として;短歌・俳句をよむ若者とは?―千四百人の高校生調査から;短歌・俳句・コピー ほか)
2部 短歌論(代表作とは何か―選ぶ主体・根拠・特性という論点;短歌とイデオロギー―フェミニズムを例にして;格闘技をうたう歌;時評(二〇〇〇‐二〇〇七年) ほか)
著者等紹介
大野道夫[オオノミチオ]
第7回現代短歌評論賞受賞(1989年)。大正大学人間学部教授(社会学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
35
#河野裕子 #短歌 しっかりと飯を食わせて陽にあてしふとんにくるみて寝かす仕合せ #返歌 まんきつで朝食食べ放ベランダで日向ぼっこし昼寝す幸せ 前著「短歌の社会学」がしっかりした本だったので安心して読めた。p202フェミニズムで取り上げている歌。2016/01/27
かふ
18
「社会学」がイデオロギーなので、短歌のような文化の領域とは相反するという保守的な指摘もあろうが、この本ではその歩み寄りを目指している。それは、イデオロギーは「人間・社会・自然についての一貫性と論理性を持った表象と主張の体系」を言うことは、短歌の文化と相反することでもない。ただそこに個人的な趣味(好き嫌いの感情)があり、例えば河野裕子がフェミニズムからなされる批評に対して「イズムのために、短歌を作っていない」というときもそこに隠れたイズムがあるのも事実である。そのことが新保守主義を蔓延させている社会なのだ。2023/01/30