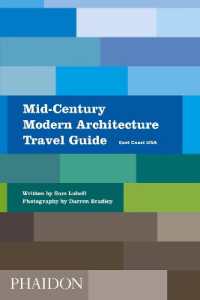内容説明
琉球石灰岩、赤土、島尻マージ、鐘乳洞、港川人、リュウキュウジカ、ムカシマンモスなど、三億年の記憶をさかのぼる“琉球列島の地史”の決定版が最新の研究成果を加えて新書で登場。深い海の底から大陸の時代、半島の時代を経て、サンゴ礁の島じまへ、琉球列島の生い立ちを知るはるかなる時の旅へ誘う一冊。
目次
第1章 青い海・白い砂浜―サンゴ礁の島じま
第2章 サンゴ礁の海から陸へ
第3章 人びとの暮らしと石―琉球石灰岩について
第4章 赤土は語る
第5章 琉球石灰岩とウルマ変動
第6章 島尻海の時代
第7章 沖縄の火山活動
第8章 沖縄の石炭時代
第9章 琉球列島の「動」と「静」
第10章 大東島の大移動
第11章 恐竜時代の沖縄―プレートがつくった島の土台
著者等紹介
神谷厚昭[カミヤコウショウ]
沖縄県那覇市首里生まれ。1967年広島大学大学院理学研究科地質鉱物学専攻修士課程修了。2003年県立真和志高校を最後に定年退職。現在、白保竿根田原洞穴遺跡調査指導委員会委員、新沖縄県史編集専門委員会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
44
【沖縄33】沖縄の地学の本。サンゴ礁がどのように沖縄の大地をつくったのかが、「サンゴとサンゴ礁のはなし」【沖縄32】でよくわからなかったので(生物学の本なのであたりまえだが)、本書を少し覗いてみたのだが、意外に面白く読み切ってしまった。名著と言って良いかもしれない。サンゴ礁が沖縄の大地をつくったメカニズムはもちろんのこと(要はサンゴ礁が堆積した地層が100万年前に隆起して琉球石灰岩となった。沖縄本島南部がこれに覆われていて、侵食しやすいので山がない)、100万年前どころか3億年前までの沖縄の姿が地層と↓2021/12/02
文章で飯を食う
9
あんまり期待せずに読んだが、割りと面白かった。現代から過去に遡り、また、過去から現代にたどるのも、良かった。しかし、南北大東島は文化的にも沖縄とは違うが、地質的にも違うんだね。2017/05/07
モンジー
0
首里城、今帰仁城の石垣に興味を持って読んでみた。沖縄の成り立ち、サンゴ礁についてなど、よくわかった。 誤字などの誤植がいくつかあったのが残念。2017/05/04
-

- 電子書籍
- ラブラッシュ! 2 ジャンプコミックス…