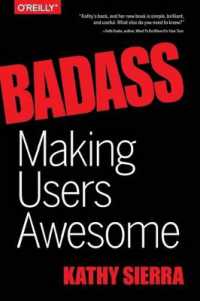内容説明
忍び寄る戦争の足音、大人たちのふるまいと隠された真実、空襲、敗戦、そして飢え。戦後の映画界になくてはならなかったひとりの女が、東京‐パリを舞台に克明に描く、その喜びと悲しみ、そして決心。胸を揺さぶる、ドラマチックな自伝的小説。
著者等紹介
秦早穂子[ハタサホコ]
1931年7月31日、東京・渋谷生まれ。洋画配給会社「新外映」の企画課長。ルネ・クレマン『太陽がいっぱい』、ロジェ・ヴァディム『危険な関係』、ゴダール『女は女である』など、数々の名作を日本に輸入した。カンヌ国際映画祭に2003年まで通い、ジャーナリストとして外国映画の紹介に努め、現在も朝日新聞の映画評のメンバーである。同時に、シャネル、マダム・グレなど、ファッションも紹介しながら、新聞、雑誌などで執筆活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
団塊シニア
7
主人公萩秋子は満州事変の年に渋谷で生まれた。筆者の自伝的小説で映画評論家でヌーベルヴァーグを日本に紹介した人物である。2012/05/20
グラコロ
3
戦後まもないパリで女ひとりしっかり仕事をする。カッコ良すぎる~。しびれる~。グラコロ堂〈人生で影響を受けた100冊〉 https://bookmeter.com/users/626279/bookcases/11552173 2013/05/17
ひとみ
2
映画のバイヤーとしてヌーベルバーグを日本に紹介した著者による自伝的小説。家族や少女〜現在の間に知り合った人々について語る「舟子」と、目的もよくわからないままいたパリで新しい才能が出現する様子を見ていたより回想記的な色の強い「私」とのパートが交互に配置され、最終章で纏まる構成が面白い。影の部分とは、歴史や人生のある局面決して表立っては語られない部分の色の濃さを指すのだろうか。小説としても文化史の記録としても読み応えのある本だった。2012/12/07
Takehiko Hosoda
1
50年代から60年代にかけてフランス映画を日本で配給する影の部分はこんな人がいた。戦後間もない時期、映画の買い付けが職業としては世間体は冷たいでしょう。ゴダールのデビュー作が日本でこれだけ指示を得ているのは筆者による邦題の力が大きいと思います。2013/03/31
田中寛一
1
映画「勝手にしやがれ」を世界で初めて買い付けたり、「太陽がいっぱい」を日本に輸入するなどで活躍した秦早穂子さん著作。満州事変の年に生まれ、太平洋戦争、戦後を、子供時代を萩舟子として描き、戦後の映画にまつわる話を私として描く。子供時代も決して暗い影ばかりではなく、父の周りの著名文芸家が登場し、華やかさもある。その中で佐藤春夫の詩「秋刀魚の歌」には春夫と谷崎潤一郎と両者の夫人が関係していることを初めて知る。改めて詩を読み直した。映画に関係しては多くのフランス映画と監督、俳優が登場する。華やかな仕事だがそこにも2013/01/03
-
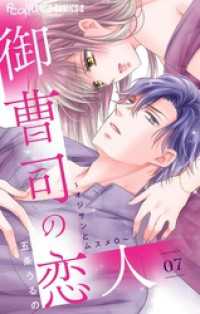
- 電子書籍
- 御曹司の恋人~オジサンとムスメ0~【マ…