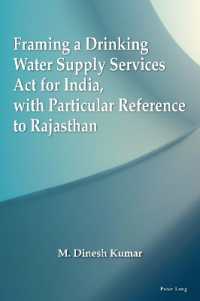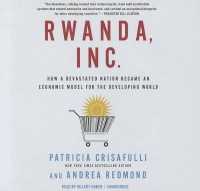内容説明
正倉院白瑠璃碗をはじめ最新の研究成果を満載し、紀元前から近代までの世界の切子ガラス名品を網羅。
目次
1 世界の切子―古代・中世(アッシリア;アケメネス朝ペルシア;ヘレニズム;ローマ;ササン朝ペルシャと中央アジア;イスラム)
2 世界の切子―近世(ヴェネツィア―近世欧1;ドイツ、ボヘミア、オランダ、イギリス―近世欧2;中国漢、清)
3 日本の切子(古代―平安時代;江戸時代)
4 切子の技法(カット、カッティング―切削;エングレイヴ、エングレイヴィング―彫削;エッチ、エッチング(喰削))
著者等紹介
谷一尚[タニイチタカシ]
昭和27年(1952)岡山市生まれ。東京大学文学部考古学科卒業、同大学文学博士。共立女子大学大学院教授、日本ガラス工芸学会会長、日本学術会議東洋学委員等を経て、現在、岡山市立オリエント美術館長
工藤吉郎[クドウヨシロウ]
昭和6年(1931)大分竹田市生まれ。東京慈恵医科大学大学院(社会医学系衛生学専攻)修了、同大学医学博士。聖マリアンナ医科大学衛生学主任教授、理事、図書館長、MEDICHEM国際会議理事、同大学客員教授、ポルフィリン研究会会長等を経て現在にいたる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遠い日
6
切子というと日本というイメージで勝手に感じていましたが、こうして紹介されれば、なるほど、世界にこんなにたくさんあるのだと理解しました。歴史的な解説、紹介、分類は、素人にはちょっと小難しく感じましたが、ガラスという素材に美を見出し、追求してきた古代からの人々の感覚が今に通じることに不思議を感じます。2018/11/14
tama
4
図書館本 切子好きだし、眼休めとしても 書架で パラパラめくって借りるの決めたので内容をちゃんと確認しなかった。世界の現代切子が見られるかと思いきや、せいぜい近代までしか載ってなかった。「鋳造ガラス」初めて知った。石膏などの型に流し込むらしいが、ガラスが流れる!?青銅の溶融音頭1250℃ 鋳鉄は1200℃ ガラスは低くくとも1200℃。十分な加熱できないから金属のようには流れないし、器作るなら中子型必要でしょ。厚肉にして削って薄くなんて、C:P比物凄く悪いぞ!薩摩長州ガラス知らんかった。へええ。2021/01/07
kinaba
1
工芸的な側面よりは歴史的な側面からの分別紹介という趣がつよい2015/07/07
Book shelf
0
書名の通り世界中の、そして古代から現代までの主流なカットガラスが出てきます。切子といえば日本の江戸切子、正倉院の白瑠璃碗といったカットガラスを指すことが多いですが、本書ではさらに広げて彫刻(エングレーヴィング)されたガラスにも触れています。 写真も豊富です。そして、近年の化学分析が活発に行われていることを受けてか、化学成分(Mg, Kなど)が掲載されているものもあるのが印象的でした。ページ数は多くないのでさらっと読むことができます。2011/11/06