- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学内科系
- > 脳神経科学・神経内科学
出版社内容情報
《内容》 歴史がわかればこんなにおもしろい!
歴史から最新トピックスまで一気に学べる,シリーズ第3弾!!
多様な脳神経科学も,歴史からひも解けばすんなり理解できます!
ニューロン命名に始まる100年の歴史から,最先端の解析技術までをダイジェストにご紹介.
アプローチに富む脳・神経科学のエッセンスが,本書でまるごと理解できます!
《目次》
歴史編
1.研究の歴史
脳神経研究100年の歴史
1.神経興奮とシナプス研究の歴史
2.脳および中枢神経機能研究の歴史
2.革新的実験法から最新技術まで
神経科学を拓き,支えている先導的研究手法
1.目的にあう標本を手にする
2.よく見る
3.生きた活動を記録する-分子・細胞,そして脳丸ごとのレベルで
4.操作・撹乱を加える
レビュー編
第1章
脳神経系の機能形態学-神経細胞の発火の時空間的パターン
1.純タンパク質性プローブ
2.膜電位センサー
3.Ca2+センサー
4.シナプス伝達のセンサー
第2章
脳・神経系の発生学-脳はどのようにしてできるのか?
1.神経管のパターン化による脳の領域形成
2.神経細胞の増殖と分化
3.発生中の大脳皮質におけるニューロンの移動
4.最近の知見と今後の展望
第3章
神経回路形成
1.神経回路の形成に必要な要素
2.軸索ガイダンス分子の多様性と作用様式
3.今後の展開
第4章
イオンチャネルと神経情報伝達
1.イオンチャネルとは
2.神経情報伝達の基本
3.薬剤のターゲット
4.神経細胞活動のシミュレーション
5.今後の研究の1つの方向性-神経細胞集団の解析
第5章
シナプス伝達と可塑性の新しい概念
1.カンナビノイドを介したシナプス前性の可塑性制御機構-シナプス後部から前部への逆行性伝達
2.グルタミン酸受容体を介したシナプス後性の可塑性制御機構-受容体の数による伝達調節
3.今後の研究の展開
第6章
遺伝子操作動物を用いた脳研究
1.遺伝子操作動物を用いた脳研究の歴史
2.遺伝子操作マウスを用いた小脳の機能解析
3.今後の研究の展開
第7章
高次脳機能を探る-帯状皮質運動野を例として
1.帯状皮質運動野の神経連絡
2.帯状皮質運動野の機能的役割
3.今後の研究の展開
第8章
脳神経疾患研究-神経系の遺伝性変性疾患を中心に
1.病気を科学する
2.機能解剖学と病気
3.異常沈着物.封入体の科学
4.ポリグルタミン病-ヒトの遺伝学によって初めて明らかにされた新たな突然変異
5.筋ジストロフィー-ポジショナルクローニングの衝撃
6.イオンチャネルと病気-チャネル病
6.RNAと病気
UP TO DATE
最新トピックス
1.おとなでも起こる神経新生
2. 神経を発生させる遺伝子が精神も司る
3. タンパク質も分解する軸索ガイダンスシグナル
4.脂質ラフトは成長円錐による軸索ガイダンスの担い手
5.ガイダンス分子受容体がR-RasのGTPase活性化タンパク質そのものだった
6.多才なCRMP2-軸索応答媒介と細胞極性にかかわる多機能分子
7.新規イオンチャネル,TRPチャネルファミリー
8.生きた神経細胞の電気活動を見る技術,スライスパッチ
9.神経細胞の電気的活動のシミュレーションーその基本的な考え方
10.生体内の神経活動をまねる手法,ダイナミッククランプ
11.イオン透過型グルタミン酸受容体の隠れた機能
12. AMPA受容体をシナプス後膜に集める分子群の発見
13.遺伝子発現の誘導・停止でわかった記憶のメカニズム
14.統合失調症モデルマウスの開発
15.シナプスを乗り越えて染色する-トランスシナプティックラベル法
16.報酬のためにがんばる強化学習
目次
歴史編(研究の歴史―脳神経研究100年の歴史;革新的実験法から最新技術まで―神経科学を拓き、支えている先導的研究手法)
レビュー編(脳神経系の機能形態学;脳・神経系の発生学;神経回路形成;イオンチャネルと神経情報伝達 ほか)
UP TO DATE―最新トピックス
著者等紹介
真鍋俊也[マナベトシヤ]
東京大学医科学研究所基礎医科学部門神経ネットワーク分野教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 戦争めし 11 ヤングチャンピオン・コ…
-
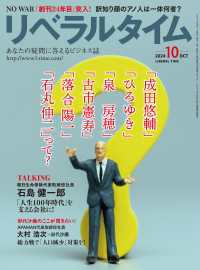
- 電子書籍
- リベラルタイム2024年10月号






