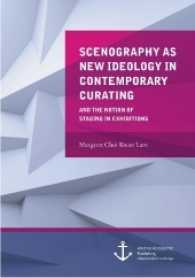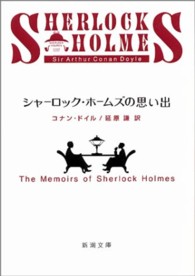出版社内容情報
《内容》 ゲノミクス・プロテオミクス技術やバイオインフォマティクスの発達により,細胞内で複雑に相互作用するシグナル伝達経路の真の姿がようやく見えてきた!
細胞周期や免疫などの多様な生命現象は,シグナル伝達によってどのように制御されているのか?シグナル伝達系の破綻による各種疾患の発症メカニズムはどこまでわかったのか?
躍進をつづけるシグナル伝達研究の最新の研究成果が効率良く理解できるレビュー集!
《目次》
序
概論:新たな方法論とともに展開するシグナル伝達研究
第1章 シグナル伝達の主要因子・経路
1. Gタンパク質とその調節因子の多様性と機能-三量体Gタンパク質の新たなシグナル伝達系
2. MAPキナーゼカスケードの多様な役割
3. チロシンキナーゼのシグナル伝達
4. NF-κBシグナルの制御メカニズム
5. TGF-βスーパーファミリーのシグナル伝達
6. Aktの活性化因子と哺乳類における機能
7. Notchシグナル伝達のしくみと役割
第2章 生命の形と機能を司るシグナル伝達
1. DNA損傷により誘導されるシグナル伝達ネットワーク
2. 分裂期キナーゼPlk1シグナル-癌化との関連を中心に
3. Wntシグナル伝達経路研究の最近の進歩
4. 細胞間接着分子とシグナル伝達-ネクチンとネクチン様分子の機能と作用機構
5. タンパク質の寿命・動態・機能を制御するユビキチンシグナル
6. SOCS遺伝子によるサイトカインシグナルの制御
7. TLRシグナルと自然免疫
8. Sonic HedgehogとGli3の終脳発生過程での役割
9. 骨制御シグナルの新たな展開
10. 生物時計システムにおけるリン酸化の役割
第3章 シグナル伝達研究における新たなアプローチ
1. トランスクリプトーム解析による血管内皮細胞シグナル伝達研究
2. プロテオミクスによるシグナル伝達ネットワークの研究
3. シグナル伝達研究のためのインタラクトーム解析
4. シグナルからシステムへ-新しい知識基盤の登場
5. 情報伝達分子の生細胞イメージング
6. バイオプローブの探索と細胞内標的分子の同定
第4章 シグナル伝達の異常による疾患・臨床応用
1. 核内受容体シグナルと疾患
2. 糖尿病とインスリンシグナリング
3. 血管新生のシグナルと,その破綻による各種疾患
4. p53ファミリーのシグナル伝達による癌抑制のメカニズム
5. gp130シグナルの異常とリウマチ様関節炎
6. 神経シグナルと神経精神疾患
目次
概論 新たな方法論とともに展開するシグナル伝達研究
第1章 シグナル伝達の主要因子・経路(Gタンパク質とその調節因子の多様性と機能―三量体Gタンパク質の新たなシグナル伝達系;MAPキナーゼカスケードの多様な役割 ほか)
第2章 生命の形と機能を司るシグナル伝達(DNA損傷により誘導されるシグナル伝達ネットワーク;分裂期キナーゼPlk1シグナル―癌化との関連を中心に ほか)
第3章 シグナル伝達研究における新たなアプローチ(トランスクリプトーム解析による血管内皮細胞シグナル伝達研究;プロテオミクスによるシグナル伝達ネットワークの研究 ほか)
第4章 シグナル伝達の異常による疾患・臨床応用(核内受容体シグナルと疾患;糖尿病とインスリンシグナリング ほか)
著者等紹介
山本雅[ヤマモトタダシ]
1972年大阪大学理学部卒業。米国国立癌研究所(NCI)研究員、東京大学医科学研究所助教授を経て’91年より同研究所教授。2003年より同研究所所長。この間、レトロウイルスLTRの転写能の解析やsrcファミリーならびにerbBファミリー癌遺伝子の構造と機能の解析を進めてきた。現在は細胞増殖抑制性Tobファミリータンパク質や細胞周期のM期を制御するキナーゼについて研究を進めている。また、チロシンリン酸化反応が中枢神経系で果たす役割についても研究を進めている
仙波憲太郎[センバケンタロウ]
1988年東京大学理学系研究科修了(理学博士)。東京大学理学部生物化学科卒業(岡田吉美教授)。植物ウイルスの研究室で、初めて遺伝子のクローニングを体験させてもらう。その後、東京大学医科学研究所制癌研究部(現癌細胞シグナル分野)でチロシンキナーゼerbB2、fynの研究を行った。山本雅所長にはこの時からご指導をいただいている。制癌研究部助手を経て、分子発癌分野助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。