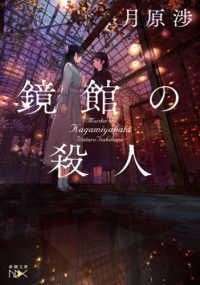出版社内容情報
宮本常一にとって「瀬戸内海の研究」は終生のテーマであった。
陸路が発達するまで、古来日本の交通・流通の大動脈として機能していた瀬戸内海は、古くから文化が開けていて、それが大小あわせて3,000もの島や周囲の環境と一体をなしている。景観はシーボルトやトーマス・クックを始め、多くの欧米人からも高く評価され、今なお風光明媚な地域である。平安末期に平清盛が航路を整備、鎌倉~戦国時代にかけては海賊衆が航路を制御下においた時期もあるが、幕末には長崎発の外国船が航海するなど、瀬戸内海は交通・流通の主役を務めていた。瀬戸内の歴史・文化・往来・漁業とくらしを見てゆく。
【目次】
瀬戸内海・いまむかし / 瀬戸内の文化 / 瀬戸内往来 / 内海の漁業とくらし / 安芸と備後の漁村と漁業
内容説明
3000もの島々・漁業と暮らし・船の変遷・海賊(村上・大内の抗争)・瀬戸の船旅・製塩など。宮本常一にとって「瀬戸内海の研究」は終生のテーマであった。
目次
瀬戸内海・いまむかし(瀬戸内海の島じま)
瀬戸内の文化(人の移動;瀬戸の物売り ほか)
瀬戸内往来(地乗りから沖乗りへ―造船と航海の発達;粥をたく船 ほか)
内海の漁業とくらし(瀬戸内海の漁業;内海の漁師たち ほか)
安芸と備後の漁村と漁業(海岸の生活とその環境;島の生活 ほか)
著者等紹介
宮本常一[ミヤモトツネイチ]
1907年、山口県周防大島生まれ。大阪府立天王寺師範学校専攻科地理学専攻卒業。民俗学者。日本観光文化研究所所長、武蔵野美術大学教授、日本常民文化研究所理事などを務める。1981年没。同年勲三等瑞宝章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
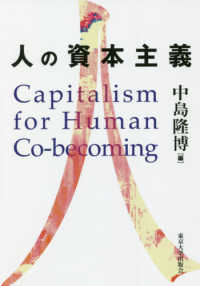
- 和書
- 人の資本主義