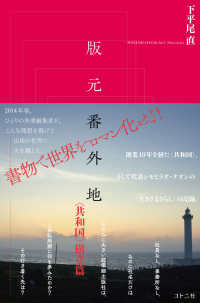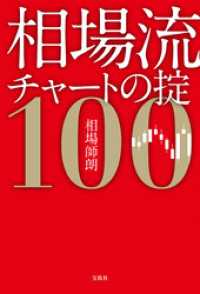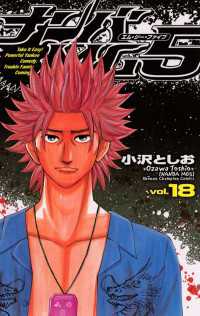内容説明
地下生菌、変形菌、冬虫夏草、地衣類など、マイナーだけど不思議なキノコを取り上げ、今も次々に新たなことがわかりつつある、菌と様々な生き物とのつながりというホットな話題を、ゲッチョ先生が体験をもとにやさしくレクチャーします。驚きに満ちた、いとも多様な共生関係。興味津々、見えない世界を覗いてみよう!
目次
第1章 地下のキノコを見る眼鏡(地下生菌屋と森歩き;キノコ屋は音を聴かない ほか)
第2章 あこがれのホコリカビ(変形菌へのあこがれ;動物でも植物でもない ほか)
第3章 歌う冬虫夏草(歌う冬虫夏草;マツウラさんの元へ ほか)
第4章 ゴキブリタケとシロアリタケ(ゴキブリのキノコ;ゾンビ・アント菌セミナー ほか)
第5章 不思議のキノコ(地衣類講話;元祖共生生物 ほか)
著者等紹介
盛口満[モリグチミツル]
1962年千葉県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。自由の森学園中・高等学校(埼玉県飯能市)の理科教員、沖縄大学人文学部こども文化学科教授を経て、現在、沖縄大学学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翠埜もぐら
16
2021年10月刊行と言うことでデータが最新です。物語のように人と人とのかかわりあいから、目に見えない菌の「目くるめくような」(ほんと眩暈がしそうだった)不思議な話が紐解かれていきます。変形菌から冬虫夏草そしてゴキブリタケ、最後は地衣類と話は多岐にわたりますが、全くの素人にもわかりやすくそして、「○○屋」と呼ばれる研究者達の変人ぶりと楽し気な様子が羨ましくも面白かったです。ハキリアリが弱ると栽培している菌にやられちゃうって、共生って言っても油断ならないんだね。2022/01/29
Tatsuhito Matsuzaki
14
生物を調査研究する自称「生き物屋」。 更にその専門に応じて〈虫屋〉〈鳥屋〉〈キノコ屋〉と分別されるようですが、著者の盛口さんは、沖縄大学学長(任期2022.3月迄)で、「生き物屋>何でも屋」。 本書は、キノコ等の菌類と生き物のつながりや共生関係をテーマに、地下性菌、変形菌、冬虫夏草、地衣類 について紹介解説しています。 「キノコ屋が音に無頓着なのは、当然ながらキノコは動かないし鳴かないから」と言いつつ、敢えてタイトルを「歌うキノコ」としているのは、著者の生き物屋としての深い思いからなんだと感じました。 2022/01/10
四不人
7
いつも変わらぬ盛口節で満足。今回は(真)菌を中心とした共生と寄生。最新の研究を交えているが、フィールド観察が中心な点は変わらない。内容も盛りだくさん。たしかに生えてないときの冬虫夏草がどこに居るかは前から不思議だった。変形菌に鞭毛虫様になったりウニの中に済んでたりするものがあるというのも、びっくり。盛口さんも歳を重ねて、著書に登場する人たちが段々年下になっているのに、自分を重ねてちょっとだけ寂しい。でも文章は若々しい。そこは嬉しい。2022/02/12
noko
4
この本のテーマはキノコ。しかし椎茸や松茸みたいな上にカサが広がっているのではなく、地下生菌。例えばトリュフ。冬虫夏草について本格的に学べる一冊。麦角菌、コルディセプス、オフィオコルディセプスに分けられる。とりつくホストは様々。変形菌は南方熊楠が研究していた。アメーバのようにゆっくり動く。養分が増えて育つと胞子嚢に変わる。動物でも植物でもない、アメーボゾアというグループに入っている。変形菌はサイズがとても小さいので、風で運ばれやすく固定種がなく、世界中に分布している。蝉の体内にいる共生菌は冬虫夏草の菌。2023/05/05
ひとえ
4
面白い。興味や知識の持ちようで、1つの対象から様々なことがわかる、楽しめる。そんな追体験が出来る本だった。日頃通う道すがら、地面、樹木、コンクリートブロックなどに目を向けてみようかな。そこには今まで知らなかった小さな生態系が広がっている、ような気がする。2022/03/18