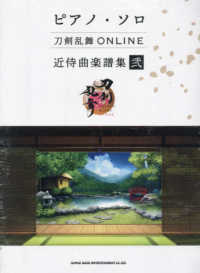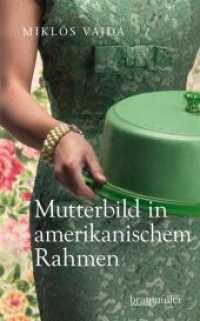内容説明
咲き乱れる桜の下に大勢が集い、思いおもいに宴を楽しむ―「群桜」「飲食」「群集」がそろった“花見”こそ、世界に類を見ない日本固有の民衆文化なのだ!!“桜花”に投影されてきた個々人の精神ではなく、“花見”という行動に映し出される集団の精神に日本文化の本質を見いだす、エキサイティングな“花見”論!!
目次
第1章 「花見」論へ―「桜」の民俗学を超えて
第2章 外国人が見た花見
第3章 世界に花見はあるか
第4章 花見と近世都市江戸―民衆的日本文化の誕生
第5章 花見の文学
第6章 現代社会と花見
終章 花見の根源を考える―社会人類学・社会心理学的花見論
著者等紹介
白幡洋三郎[シラハタヨウザブロウ]
1949年大阪府生まれ。1980年京都大学大学院農学研究科博士課程単位修得退学。農学博士。京都大学農学部助手、国際日本文化研究センター教授を経て、中部大学特任教授。国際日本文化研究センター名誉教授。主な著書『プラントハンター:ヨーロッパの植物熱と日本』講談社選書メチエ、1994年(毎日出版文化賞奨励賞)→講談社学術文庫、2005年他多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マーブル
10
現代の形の花見は江戸期に広く一般的になった。そのルーツは貴族が開いていた梅花の宴が平安時代に桜を愛でるものに変わったものと、農民が春の山に入り飲食をした「春山入り」にある。異なる身分の者が別々の仕方で桜を愛でていた訳だが、江戸でそれが大衆の娯楽となったのには吉宗の政治的施策があった。共食と贈与との関係を論じた章も興味深い。共食によって集団の一体感を得ようとするのは、何も日本に限らず世界中で見られるのだろうが、贈与論からその飲食を考えると日本に特徴的なもののようだ。宴は時と場所を同じくする贈与であるとする。2019/04/30
katashin86
0
お花見のお供に。2023/04/02