内容説明
日本の山間に住む人々はどんな暮らしをしていたのか。そして日本人は山をどのように利用していたのか。魔の谷・入らず山・女人禁制の山、クマ・イノシシ狩、落とし穴の狩猟、マタギの生活、木地屋、山村を追われ身を寄せ合い暮らしていた人々…山と日本人の関わりを調査し、考え、見てゆく。
目次
修験の峯々
魔の谷・入らず
消えゆく山民
狩猟
陥穴
木地屋の漂泊
山村を追われる者
山と人間
身を寄せ合う暮らし
豊松逍遙
信濃路
山の神楽
山村の地域文化保存について
著者等紹介
宮本常一[ミヤモトツネイチ]
1907年、山口県周防大島生まれ。大阪府立天王寺師範学校専攻科地理学専攻卒業。民俗学者。日本観光文化研究所所長、武蔵野美術大学教授、日本常民文化研究所理事などを務める。1981年没。同年勲三等瑞宝章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
飯田健雄
22
宮本常一の本を読むと、なぜ、ほっとし、癒しにつながるのだろう。もっと、年をとって、まだ歩けるようだったら、彼がフィールドワークした土地にいってみたい。彼の本は、酒と非常にマッチする。2016/06/12
1.3manen
11
新刊棚より。1970年前後の山村の実態。谷文晁の山の線画はとてもダイナミックである。鍛冶屋、木地屋。天竜川、遠山地方が出てくる(55頁)。この間、伊那市長谷から国道152号の山道は結構キツカッタ。すれ違いしにくい狭い国道であった。10年前も浜松から水窪、南信濃のあの青崩峠辺りもすごかったが、あのままなのか? 153号、151号の方が相当マシ。クマの罠(68頁)。山に餌がなく、人里まで現れる時代だ。木地師と塗師が結合して塗り物が誕生(109頁)。協働の産物。過疎化高齢化していく山村にあって新たな文化振興を。2013/08/30
hase45
2
★★★★☆ やはり宮本常一は面白い。ここで描かれるような山間の文化が昭和40年代まで残っていたということが興味深い。2020/10/05
ホンドテン
2
図書館で。敗戦直後から晩年までの山に関する著文をまとめたもの。そのため散漫な印象もあるが、著者の見解の変遷を追う意義も編者のあとがきにもあるようにあるだろう。牧歌的な「豊松逍遙」や「山の神楽」にも「消えゆく山民」の日本残酷物語な山間の過酷な生活を想像させられた。近代化以降、山村とそれが依存する山林を構造的に変貌(荒廃)させた製紙工業の存在は恥ずべきだが新知見であり愕然とする。最後の報告文から40年超、事態の不可逆的悪化に胆が冷えるばかり。2018/02/28
Go Extreme
1
修験道の起源と歴史:山岳信仰 修験者 平安時代 鎌倉時代 大峰山 白山 信濃山岳 修行道場 霊場巡礼 修験道の宗教的実践:瞑想 祈り 山岳登攀 禁欲 祭り 儀式 精神的成長 修験行 修行体系 内観 文化的意義:自然崇拝 生命の源 地域文化 民俗伝承 伝統継承 神話形成 精神的支柱 共同体形成 神聖視 現代:文化遺産保存 観光資源 精神的安定 伝統適応 信者減少 高齢化 地域振興 エコツーリズム 修行体験 課題と展望:信者減少 文化継承 現代適応 若者参加促進 観光融合 祭り活性化 継続的支援 修行の再評価2025/03/14
-

- 電子書籍
- 石見さんのGライフ 【短編】5 BC …
-
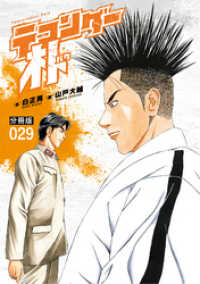
- 電子書籍
- テコンダー朴 分冊版29
-

- 電子書籍
- CHANTO 2015年 06月号 C…
-

- 電子書籍
- 「神田川」見立て殺人 間暮警部の事件簿…
-
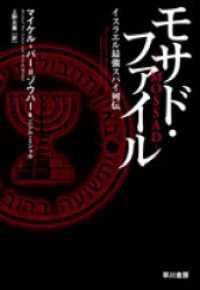
- 電子書籍
- モサド・ファイル イスラエル最強スパイ…




