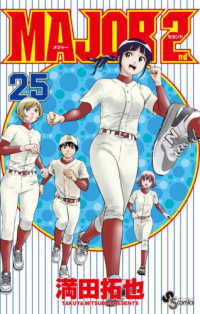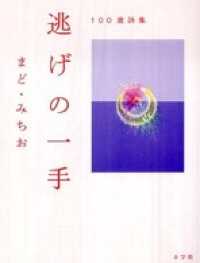内容説明
約一万年前、地球規模の温暖化に伴って、海水が陸地の奥深く浸入する縄文海進が始まった。房総半島南端の館山湾にはサンゴ礁が形成され、鎌倉の鶴岡八幡宮や大仏境内は波打ち際だった。六〇〇〇年前には、現在より二~三メートル高い位置まで海が広がり、複雑な海岸線をもつ入江には多種多様の貝が生息し、台地上には多くの貝塚がつくられた。本書は、当時の海に生息していた貝の化石と貝塚の貝をもとに、海流や海水温の変化を明らかにし、相模湾・東京湾沿岸の縄文時代の海岸線や古環境を復元する。
目次
1 貝からのメッセージ
2 相模湾沿岸の海岸線の変遷
3 東京湾沿岸の海岸線の変遷
4 房総半島南端―サンゴ礁が発達する暖かな縄文の海
5 南関東における海進最盛期以後の地殻変動
6 伊勢湾知多半島で明らかになった縄文海進の記録
7 温暖種からみた日本列島沿岸の環境の変化
8 日本列島で明らかになった温暖種の消長
9 ハワイ諸島カウアイ島における完新世の高海面の発見
著者等紹介
松島義章[マツシマヨシアキ]
1936年長野県生まれ。横浜国立大学学芸学部地学科卒。神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員、放送大学大学院客員教授。専門は古生物学、第四紀地質学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メロン泥棒
1
縄文海進についてかなり詳しく書かれた1冊。新書ながらも専門的すぎて、素人の自分には表面しか読めなかった。著者は貝塚の分布などから縄文時代にどこまで海が来たかという問題について解析しており、過去を掘り起こして推測することの大変さがよく伝わってくる。縄文時代の海岸線はこんな感じでしたと言って見せられる絵一枚にこれほど綿密な調査がベースにあるとは驚かされる。2011/12/18
snsk
1
思ってたよりも専門的で難しかったのでナナメ読み。まあ極論すれば縄文海進の時代のことを考えれば、今の温暖化による水位上昇なんてかわいいものなわけですね。それでも人間は生きていけるってことなのかも。2009/01/15
furugenyo
0
むうぅ、論文。。もっと広範囲に、(この表紙のような)当時の海岸線の絵が見たかったのだ。2010/06/15