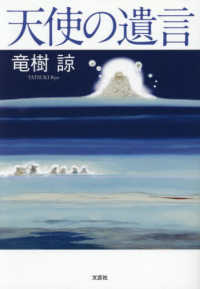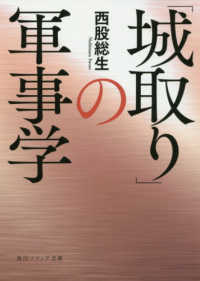内容説明
18C初頭独逸辺境であろうか。霧の濃い黒い森の中に優美な城館が佇む。旅人を誘うかのように城の扉は半ば開いていた。亡霊が支配する城壁の内側は生きる習慣を失った植物。永劫回帰の罠に捉われた時間、森の中の不安な孤独を超え、自分自身を再び見出すイニシエーションの旅。
著者等紹介
ブリヨン,マルセル[ブリヨン,マルセル][Brion,Marcel]
1895~1984。アイルランド系の父と南仏に先祖を持つ母の間にマルセイユで生れ、ラテン的知性とゲルマン的感性の対話の中に育つ。その広範な知識から美術評論家、考古学者、伝記作家、歴史家、小説家と多様な場面で活躍し、1964年アカデミー・フランセーズに入会
村上光彦[ムラカミミツヒコ]
1929年、佐世保に生まれる。1953年、東京大学文学部仏文学科卒業。成蹊大学名誉教授、大佛次郎研究会会長、鎌倉ペンクラブ副会長。訳書『ド・ゴール大戦回顧録』(共訳、1960‐1966)で1968年度ポール・クローデル賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
194
花盛りのツツジ、暗緑のマロニエ、青い空…全てが支え合う景色。この美しい景色は語り手にとって醒めた眼で見る夢、触れることを自ら禁じた夢なのだ。馬に乗った辺境伯とその夫人や娘たちを遠くから見ては、書物を介して貴族の男と交流するのみ。彼らの留守に城館を訪れるが、そこへの帰属や理解は拒まれており、案内者の少女も遠くから「体温」を届ける配達人にすぎない。むしろ彼方此方に現れる霧や薄闇こそ再創造の契機に思える。語り手の夢を追ううちに、いつしか《止まった噴水が輝かしい死と化して空を目ざす正午》を待ち望んでいた。19432021/10/14
mii22.
55
至福の読書時間を求めて再読。夏の始め、旅人と私は、霧深いすべてが幻のようなこの場所に誘われるようにやって来た。城壁の内側にひろがる林苑をひと夏の間彷徨続ける旅人と私。そこで目にした音楽堂、中国庭園、数々の彫像たち、噴水、迷路、塔、教会。時には森の城館の住人たちとも出くわすが..夏の終わりにはこの世界から旅立たなければならないことは感じていた。霧のなかから現れ霧のなかに消えていく幻の林苑と城館。2018/08/12
HANA
55
筋らしい筋は無く主人公が城館の中を彷徨う話なのだが、読んでいるうちに読んでいる自分も薄明の霧の中のような城館内部を彷徨っているような感覚に襲われる。登場人物も全て浮世離れしており、まるで影絵芝居を見ている様。ほとんどの場面が城館の描写に費やされているが、そのためか場面場面でまるで絵を見ているような気分にさせられた。それが一番印象的なのは霧の中の馬車の場面。未生の闇の中で見る夢のような場面は一読忘れがたい。城館の様子をひたすら鑑賞するような本だったが、その静謐な文章は実に穏やかな読書時間をもたらしてくれた。2015/10/01
mii22.
50
夏のはじめ、誘われるように半開きの扉をひとりの旅人がくぐり抜け城壁の中に入ると、そこに広大な林苑と優美な城館が霧の中から現れた。旅人はひと夏そこに滞在し林苑の中を毎日彷徨する。甘美で静寂で心惹かれる世界だが、物語の中をさ迷い歩くと、時折胸騒ぎをおぼえ不安な気持ちになり怯えたりする。存在と非在、現実と夢の中間の時空に身を置くような不思議な感覚。まるで詩のようなブリヨンの美しい文章を浴びるように読んでいると、もうこの世界から離れたくないそんな気持ちにさせられる。至福の読書時間を夏の終わりにもう一度味わいたい。2016/07/31
藤月はな(灯れ松明の火)
36
幻影の城舘の娘に恋した男は通い詰めるようになるが・・・・。館に集うこの世の者ではないものたち、混雑する記憶、冷たくなったり、情熱的に迫ったりする娘に戸惑う男とこの世にあるとは思えない位、現実味のない館の描写は「去年、マリエンバートで」のよう。館の食事はギリシャ神話でぺロポネスが食べた柘榴、伊佐那美の黄泉戸喰、「家守綺譚」の湖の底の葡萄と重なります。その場に属す物を食さなかった者はアダムとエヴァの逆説のような理論で追放される。後に残るは孤独でも安らかな静謐ばかり。2013/06/25