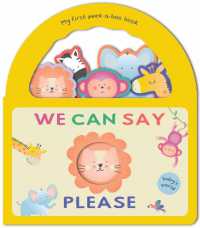内容説明
祝日や季節の行事をひも解き、由来を知ると、自然とかかわりながら積み重ねてきた生き生きとした日本人の暮らしが見えてきます。現代の私たちの暮らしにも取り入れたい知恵がたくさんあります。
目次
1月(元旦;お正月に「おめでとう」と挨拶するのはなぜ? ほか)
2月(節分に鬼があらわれるのはなぜ?;建国記念の日 ほか)
3月(ひな祭りのそもそもの意味とは?;春分の日 ほか)
4月(お花見に宴会がつきもののわけは?;花鎮めとは? ほか)
5月(憲法記念日;みどりの日 ほか)
6月(年に二度ある節目の祓いとは?;茅の輪くぐりとは? ほか)
7月(七夕の物語の由来とは?;七夕に竹や笹を使うのはなぜ? ほか)
8月(山の日;夏祭りにはどんな意味があるの?)
9月(重陽の節句に菊が使われるのはなぜ?;敬老の日 ほか)
10月(「神あり月」と呼ぶ地方はどこ?;スポーツの日)
11月(文化の日;七五三のお祝いに込められているものとは? ほか)
12月(冬至にユズ湯に入り、カボチャを食べるのはなぜ?;年越しそばを食べるのはなぜ? ほか)
著者等紹介
生方徹夫[オブカタテツオ]
民俗学者。1931年、佐賀県生まれ。69年、國學院大學大学院修士課程修了。77年から麗澤大学外国語学部講師、助教授を経て、85年から教授(民俗学・日本語)。2021年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Dramaticseimei
8
日本の年中行事がいかに古来からの日本人の生き方と密接に関係しているかがわかる。当たり前にご飯を食べられる時代は幸せには違いないが、その当たり前に至るまでの果てしない道のりに感謝をしなくなってしまっている現代には魂が宿らなくなってしまっているようには感じる。形式ばかりのものだけを楽しみ、魂が抜けてしまったこの生き方にいずれ大きな災いが起きても不思議はない。たかが80年。積み重ねた歴史を破壊し続けてることが幸せにはならないことをようやく少し気づいてきている2025/12/27
スプリント
8
季節感がどんどんなくなっているので改めて歳時の由来を学ぶことができた。2022/05/29
ゆり
2
日本の祝日の由来がわかりやすく書いてあり、参考になった 行事を大事にできるようになりたい2023/10/25
Go Extreme
2
1月 初詣はなぜするの 2月 節分に鬼があらわれるのはなぜ 3月 ひな祭りのそもそもの意味とは 4月 お花見に宴会がつきもののわけは 5月 憲法記念日 6月 茅の輪くぐりとは 7月 七夕の物語の由来とは 七夕に竹や笹を使うのはなぜ お盆にはどんな意味がある 8月 山の日 夏祭りにはどんな意味があるの 9月 重陽の節句に菊が使われるのはなぜ 月の呼称がたくさんあるのはなぜ 10月 「神あり月」と呼ぶ地方はどこ 11月 新嘗祭はどんなお祭り 12月 冬至にユズ湯に入り、カボチャを食べるのはなぜ2022/01/26
卓ちゃん
1
六曜がどのような規則で並べられているか、除夜の鐘でつく人間の煩悩の数とされる百八回がどのように算出されているか、旧暦・新暦がどのような過程でできたか、などがよくわかった。暦は12の月、24の節気、72の候に複雑に分けられているが、私たちの「生活の指針であり、季節を知らせて、生き方を示すもの」となっている。読み終えて、子どもの頃のことが懐かしく思えた。著者が亡くなられた後、再編集のうえ発行されたようである。ご冥福をお祈り申し上げます。2022/02/19