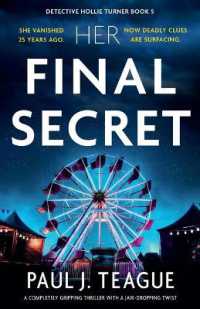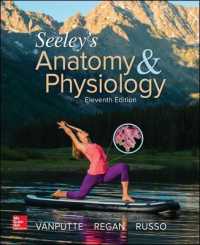内容説明
インドの伝統工芸、カラムカリのつくり手たちは、なぜ自らを「アーティスト」と名のるのか―19世紀頃から寺院に掛けられる布として伝わり、20世紀半ば、政府の手工芸振興策によって、からくも消滅を免れたカラムカリ。技術を継承する製作者たちは、カーストや帰属が混在し、女性が参入し、技術的差異が広がって、多様化が進む。師のもとで修業に励むかたわら著者は、彼らの語りに耳を傾け、つくる身体に生成された意識を追い、つくり手としての座標を解き明かす。
目次
1 手工芸開発について(一九五〇年代の手工芸振興の役割;カラムカリ・トレーニングセンター閉鎖と以後の変遷)
2 カラムカリ技術(「伝統的」技術習得過程;技術習得における変化;つくる側にとっての「伝統性」)
3 製作者の多様化とその分類(技術習得状況と製作者の多様性の関係;女性製作者の多様化)
4 つくり手としての自己認識の生成(手工芸への西洋美術概念の波及と「インドらしさ」の見直し;カラムカリ製作者の自己表象の選択;製作者意識の鍵概念―「創造力・想像力」「宗教性」;自己認識の生成過程)
著者等紹介
松村恵里[マツムラエリ]
1967年、石川県生まれ。染織を学んだ後、友禅作家押田正義、二塚長生(重要無形文化財)に師事。金沢大学人間社会環境研究科博士後期課程修了、博士(社会環境学)。現在、金沢大学国際文化資源学研究センター・特任助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。