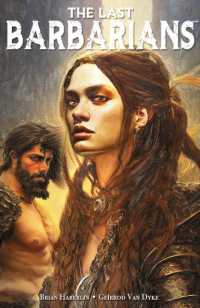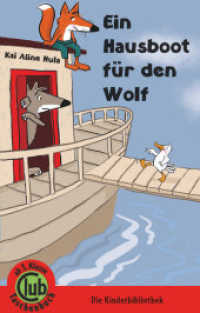出版社内容情報
《内容》 監訳者序文 近年の遺伝子工学の急速な進歩には目をみはるものがあるが,その臨床への積極的な応用により,21世紀初頭にはさまざまな疾患に対する治療法が一変する可能性もある.心臓病の診断や治療の分野においても,この大きな流れに沿って研究が進んでいくことが予想されるが,一方では,これまで積み重ねられてきた循環生理,電気生理に関しての知識の基盤があってこそ,初めて新しい研究が生まれ,正しい進歩・発展を遂げていくものであるともいえる. 本書を初めて手にしたときの第一印象は,贅肉のないシンプルな記述によって心臓の生理学,薬理学のほぼ全分野を網羅していることと,図表が明瞭でわかりやすいことの2点で,これから心臓生理学を学ぶ医学生のためのサブテキストとして,あるいは研修医のための基礎知識のまとめとして適しているのではないかというものであった.しかし翻訳作業を進めていくにつれ,記述内容がたいへん正確であること,現象の説明が的確で理解しやすいこと,歴史的背景から最新の研究成果まで偏りのない記載がなされていることなど,それぞれの項目についての著者の深い見識と公平なものの見方に感心した.さらには,各分野における今後の研究の方向性や予測される進歩を示唆する記述が随所に散見されたことも驚きで,単なるテキストの枠を超え,一つの読み物としても楽しめるものであった.これらの点から本書は,著者自身が序文で述べているように,医学生,研修医にとどまらず,心臓病に関連する多くの研究者やコメディカルを含めた医療従事者まで幅広い読者層に受け入れられ,そのニーズに応えられるように企画されていることは明らかである. 本書の翻訳にあたって日本医科大学第1内科の医局員数名の協力を仰いだが,いずれもそれぞれの担当分野を専門に第一線で研究を行っているメンバーで,的確な翻訳がなされていることは言うまでもなく,加えて最新の情報やわが国の現状などについても適切なコメントが付けられているものと自負している.このような点から,本書は循環生理学,電気生理学あるいは薬理学などさまざまな角度から心臓を捉え,その機能や病態に関しての正確な知識の基盤を得ることを求めている人々にとって最適の書であると思う. 《目次》 目 次 はじめに:心臓の働き 1心臓の機能的解剖 2心周期中の機械的イベント 3興奮伝導路 4心筋細胞の電気生理:心室筋と心房筋 5心筋細胞の電気生理:歩調取りおよび刺激伝導系の組織 6心電図 7不整脈:電気生理学的基礎 8抗不整脈薬 9不整脈:臨床的側面から 10心筋における興奮収縮連関と機械的電気的調節機構 11心筋収縮力 12自律神経系による心拍数と収縮力の調節 13心拍出量の測定 14心臓の環境:イオンの濃度変化の心臓への影響 15冠血流と冠血栓 16虚血性心疾患の治療薬 17心不全 18心不全の治療薬 19心臓イオンチャネルの分子生物学 20心臓研究の展望
目次
はじめに 心臓の働き
心臓の機能的解剖
心周期中の機械的イベント
興奮伝導路
心筋細胞の電気生理(心室筋と心房筋;歩調取りおよび刺激伝導系の組織)
心電図
不整脈―電気生理学的基礎
抗不整脈薬
不整脈―臨床的側面から〔ほか〕