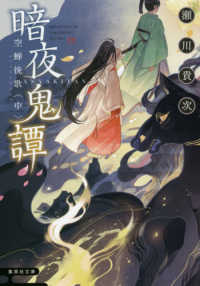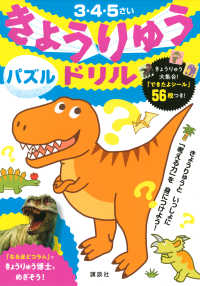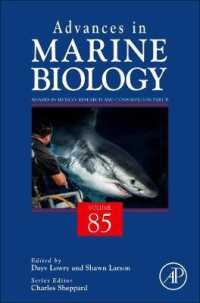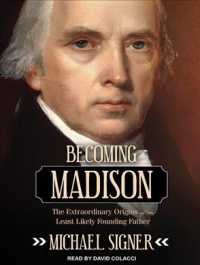- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学外科系
- > リハビリテーション医学
内容説明
いま作業療法に必要なのは“患者自身が自分と向き合える作業”を提供することである。つまり、“患者を治す視点”から“セルフヘルプペイシェントを作る視点”へのパラダイムシフトである。作業活動を提供するカウンセリング技術(認知行動療法)によって、患者に行動変容を促し、ADL、QOLともに改善できる。この効果を発揮できるのは作業療法士だけである。
目次
序章 概説―認知行動療法の概略と作業療法における効果について(作業療法士のアイデンティティと認知行動療法―なぜCBTなのか?)
第1章 認知行動療法―基礎編(身体領域作業療法における患者心理と対処;作業療法のための認知行動療法の応用基礎)
第2章 認知行動療法の応用による作業療法の実践報告(CBTと作業療法の併用により障害認識が改善されたCVA患者―一言日記で“逃避”から“目標”へ;明確な障害認識がもたらした好循環の失行事例―「できない」から機能を最大限に利用した「できるかも」へ;回復期リハ病棟に入院する患者へのCBT―患者は何を考えている?;脳卒中発症後に心理的変化から不安を訴えた事例;集団CBTの活用により行動変容した事例―他者を蹴る行動から「この人たちとできて良かった」という発言・行動の変化へ;CBTによって歩行意欲の向上につながった整形外科的疾患の事例)
著者等紹介
大嶋伸雄[オオシマノブオ]
首都大学東京健康福祉学部作業療法学科・教授、博士(医学)、作業療法士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。