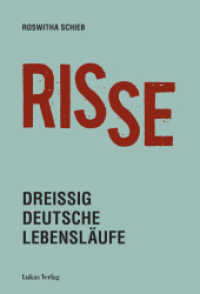出版社内容情報
アメリカで同時多発テロ! 日本も危ない!
落合信彦 推薦
「これがテロ対策の解答だ!」
今日の世界の指導者の中でもテロリズムと現場で戦った経験のあるのは恐らくネタニヤフだけであろう。 それだけにテロを憎み、テロの恐ろしさを身にしみて知る彼が記した本書は説得力がある。
2001年9月25日(火)産経新聞「産経抄」より転載
二十四日付小紙「主張」でもお伝えしたが、テロとたたかう軍事行動をテロと同じレベルの“暴力”や“報復”ととる論調が日本には少なくない。「暴力には暴力を、では果てしない報復合戦になる」などというように…。
▼多数の日本人が犠牲に なり、日本自身もテロの被害者であり、当事者であるのに、なぜこのようなテロリストを許してしまう論理がまかり通るのか。これもまた「日本が平和でありさえすればよい」という戦後民主主義の落とし子なのかもしれない。
▼そんななか、イスラエルの元首相ベンヤミン・ネタニヤフ氏が六年前に書いた『テロリズムとはこう戦え』(ミルトス刊)を読んで、教えられた。イスラエルの強硬な反テロ論者という立場を割り引いても、国際テロリズムの現場でたたかった対策が示されていたからである。
▼同氏はテロ行為にそなえる十カ条を次のようにあげていた。(1)テロ国家に核技術を提供する国に制裁を加える (2)テロ国家に外交的・経済的・軍事的制裁を加える (3)テロリストのエンクレーブ(飛び地)を制圧する (4)西欧におけるテロ政権とテロ組織の資産を凍結する。
▼(5)情報を交換する (6)テロをあおる組織の監視と対テロ行動の規模を拡大できるように法を改正し、定期的にそれを見直す (7)テロリストを積極的に追跡する (8)テロリストの囚人を釈放しない (9)テロリズムと戦う特殊部隊を養成する (10)一般大衆を教育する…。
▼急ぎ足で個条書きしかご紹介できなかったが、ここにはテロを憎み、テロの恐ろしさを身にしみて知る人が語る説得力がある。しかし日本の世論の流れは、どうやら一国平和主義に向かっているらしい。平和は願うものでなく、創るものであるはずなのに。
まえがき----落合信彦
はじめに
第1章 はびこる国内テロ
テロリズムとは何か
テロリズムの自己矛盾比
アメリカのテロは今後どうなるか
米国の新しい極右勢力
第一の防御策-民主主義の精神」
純第二の防御策-「作戦」
第2章 市民の自由にかかわる問題
二種類の対テロ戦略
市民の自由とのジレンマ
積極的対テロ行動に踏み切る時
地下鉄サリン事件での日本の対応
カナダとアメリカの場合
湾岸戦争時のテロ防止策
テロリストの権利まで保障するアメリカ
市民の自由はどこまで認められるべきか
保安当局をコントロールする西欧諸国
言論の自由は無制限ではない
第3章 1980年代--国際デロに対する勝利
国際テロの性格と生いたち
旧ソ連が育てた国際テロ組織
PL0の歴史
テロ支援国に広がったPLO
対テロリズム研究機関「ヨナタン研究所」
国際テロに勝つには
シュルツの積極的対テロ政策
断固とテロに対抗したTWAハイジャック事件
国際テロリズムに打撃を与えた80年代
第4章 1990年代--武装イスラム勢力の台頭
テロはなくならない
不徹底だった湾岸戦争後の措置
国際テロを支援するイラン
スンニー派勢力を目覚めさせたアフガン戦争
西欧に対する憎しみの歴史
汎アラブ主義とイスラム原理主義
アラブ支配者に敵対したイスラム原理主義
西欧に浸透するイスラム・テロ組織
イスラム・テロが増大するトルコ
武装イスラムの世界貿易センター爆破
「アメリカのジハド」
国際テロ拠点として都合のよいアメリカ
第5章 ガザ・シンドローム
アラブで生まれた二つの対イスラエル論
テロ基地ガザからイスラエルは撤退
PL0の本心は変わっていない
テロ活動を取締れないオスロ合意のとりきめ
アラファトのオスロ合意違反
イスラエル政府の犯したあやまち
ガザにできた自由テロ地帯
和平はアラファトの戦術だ
テロ小休止は戦術のうち
PLOはハマスと共同戦線をもくろむ
ガザはイスラム・テロの国際センターとなった
第6章 恐るべき核テロリズム
イランは数年後に核兵器を保有する
イランの石油よりも強力な武器
危険な原理主義思想
イスラム原理主義者に核兵器を持たせるな
第7章 対策
脅威の本質を知り、断固と行動せよ
テロ対策の提言
原注
訳者あとがき
まえがき
本書の著者ビニヤミン・ネタニヤフ氏に私が初めて会ったのは、1992年の春だった。その頃彼はイスラエル外務省の次官として働いていたが、前年起きた湾岸戦争の最中イスラエルの”顔”として毎日のようにCNNに出ていたため、かなり国際的に知られた存在となっていた。
実力的にも外務大臣のデヴィッド・レヴィ氏を上まわるとさえ言われていた。
洗練されたハーバード仕込みの英語とシャープな頭脳の持ち主と言うのが第一印象だった。
そのときは当時話題になっていたマドリッドでの中東和平会議の行方についていろいろと質問したのだが、彼は一貫して悲観的な意見に終始した。
二度目に会ったのは彼が外務省を辞めてリクードのトップとなったときだったが、このときもやはり中東和平やPLOとの和平プロセスについてm彼は理路整然とペシミスティックな立場を示した。
1996年6月、ネタニヤフはイスラエル建国以来初めての首相公選選挙で前任者のシモン・ペレスを破って首相となった。
このときを境にPLOとの間に進められていた和平プロセスはデッド・ロックにぶち当たった。その責任者としてアラブ各国は彼を非難し、仲介役のアメリカは当惑した。世界中が和平プロセスは逆戻りしたと考え、ネタニヤフのかたくななまでのPLO拒否姿勢を批判した。
しかし、中東和平やPLOについての彼の考えをじかに聞いてきた私にとっては別に驚きではなかった。
彼のPLOやアラブ各国に対する考えの根底には、ネガティブかつぬぐい去り難いひとつの要素があるからだ。
それは憎しみにも似た猜疑心と不信感だ。その理由はと言えば、これまでのアラブやPLOメンバーによって行われてきた数々のテロ行為につきる。
首相になってから3ヵ月後ネタニヤフはPLOの議長ヤセル・アラファトと初めて会ったが、そのときの模様を彼は”自分のこれまでの人生で最もつらいことだった”と述べたが、このステートメントを具体的に説明すると次ぎのようになる。
1967年6月27日、乗客乗組員256人を乗せたエール・フランス機がハイジャックされ、ウガンダのエンテベ空港に着陸した。
乗客のうち150人あまりが解放されたが、残りはウガンダ政府の支援と了解のもとでテロリストによってエンテベ空港に人質として残された。
イスラエルはただちに行動を起こした。情報機関は解放された乗客にインタビューしてエンテベでの人質監視態勢やテロリストの数、ウガンダ兵の持つ武器や人数などありとあらゆる事柄について聞き出した。
さらにエンテベ空港をよく知るアメリカやフランスのパイロットたちに会って詳細な空港の模型も造った。テロリストを支援するアミン大統領専用のベンツのライセンス・ナンバーまでイスラエル情報機関は握っていた。
そして7月3日未明、イスラエル軍特殊部隊は3機のC-130に乗って4千キロを飛んでエンテベ空港を奇襲した。
結果はテロリスト全員射殺、ウガンダ兵氏約100人が死亡、さらにウガンダ空軍のミグ21をはじめとする多数の空軍機が破壊され、エンテベ空港は完全なマヒ状態に陥った。
人質のうち3名は死亡したが、残りの102人は全員救出。完璧に近い成功だった。
しかし、イスラエル特殊部隊にも犠牲者がひとり出た。ヨナタン・ネタニヤフ指揮官である。
彼はビニヤミン・ネタニヤフ現首相の実兄だった(彼にちなんであの作戦は”オペレーション・ヨナタン”と名付けられた)。
このハイジャックはPLOの傘下にあるブラック・セプテンバー・グループによって進められたものだったが、このグループはPLO内最大の派閥であるファタハが武力行使に出るときに使う名前であった。
そしてファタハの最高実力者が誰あろうヤセル・アラファトだったのである。
だからネタニヤフにしてみれば、アラファトが兄ヨナタンを殺したも同然だったのだ。
これを理解すればアラファトと会って握手することが”自分のこれまでの人生で最も辛いことだった”という彼の言葉は強烈なリアリティーをおびてくる。
今日の世界の指導者のなかでも、テロリズムと現場で戦った経験おあるのはおそらくネタニヤフだけであろう。
それだけにテロを憎み、テロの恐ろしさを身にしみて知る彼が記した本書は説得力がある。
これからのテロはかつてのような人質をとるような性質のものではなく、まず破壊に走ると彼は言う。
新しいテロリズムの誕生である。アメリカオクラホマ・シティーの連邦政府ビル爆破、ニューヨークのワールド・トレード・センター爆破、パリの地下鉄爆破、東京の地下鉄サリン事件などそのやり方は無差別かつ大規模化している。
さらにはイランをはじめとする過激国家が核を保持する可能性もある。
このような超大型化するテロに、はたして西側自由社会は太刀打ちできるのか?
絶対に出来るとネタニヤフは断言する。そしてその方法を彼独特のシャープな切り口で歴史的、政治的側面から説いている。
本書の著者が単なるテロ研究家だったら、読むものにそれほどパワフルなインパクトを与えないだろう。
エンテベの勇者の弟として、そしてそのあと外交官として数々のテロに直面してきたビニヤミン・ナタニヤフが書いたからこそ抜群の説得力があるのだ。
テロを憎み自由を愛し、その自由を守る義務がある自由社会の市民全員にぜひ読んでもらいたい本である。
落合信彦
目次
第1章 はびこる国内テロ
第2章 市民の自由にかかわる問題
第3章 1980年代―国際テロに対する勝利
第4章 1990年代―武装イスラム勢力の台頭
第5章 ガザ・シンドローム
第6章 恐るべき核テロリズム
第7章 対策


![心やすらぐ、ぐっすり眠れる夢の絶景カレンダー 〈2021〉 [カレンダー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47981/4798167118.jpg)