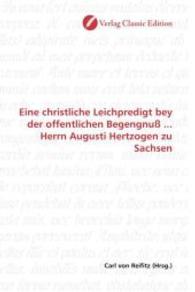出版社内容情報
ユダヤ人が聖書学の成果を踏まえて、キリスト教の聖典をユダヤ人に紹介したユニークな本。
第一部 聖書を読むまえに
1章 新約聖書の成り立ち
2章 歴史家の取り組み方
3章 ユダヤ教の背景
4章 ユダヤ教からキリスト教へ
第二部 パウロとパウロの手紙
5章 パウロ主義の背景
6章 パウロ
7章 キリストについてのパウロの見方
8章 教会とモーセの律法
9章 パウロの手紙
10章 パウロのキリスト教とギリシア宗教
第三部 共観福音書とイエス
11章 福音書の成立まで
12章 マルコによる福音書
13章 マルコによる福音書を超えて
14章 マタイによる福音書
15章 ルカによる福音書
16章 歴史上のイエス
第四部 そのほかの書
17章 公同書簡、牧会書簡、ヨハネの手紙
18章 ヤコブの手紙
19章 ペテロの第一の手紙
20章 ヘブル人への手紙
21章 ヨハネの手紙
22章 ヨハネの黙示録
23章 使徒行伝
24章 ヨハネによる福音書
25章 牧会書簡
26章 ユダの手紙、ペテロの第二の手紙
第五部 新約聖書の意義
27章 新約聖書信仰の真髄
28章 エピローグ
訳者あとがき(抄)
近年、キリスト教のルーツとしてのユダヤ教への関心が高まり、ユダヤ的背景のもとで福音書の世界を再検討することが始まっていると言われる。
その一方で、ユダヤ教はキリスト教をどのように見ているかは、両宗教の関係が論じられるとき、ごく自然に興味を引く問題である。本書は、ユダヤ人が新約聖書をどのように見ているかの格好な資料の一つである。
本書はSamuel Sandmel(1911-1979)によるA Jewish Understanding of the New Testament(1956年初版)の翻訳である。
著者サミュエル・サンドメルはアメリカ・オハイオ州出身の改革派ユダヤ教のラビで、聖書学者。改革派ユダヤ教の神学校ヘブリュー・ユニオン・カレッジを卒業し、イェール大学で博士号を修得後、1952年からずっと母校ヘブリュー・ユニオン・カレッジで聖書とヘレニズム文学の教授を務めた。
サンドメル教授の関心は一貫してユダヤ教と新約聖書の関係であった。本書を皮切りに、次々と新約聖書関係のテーマの著作を世に出し、国際的にもこの分野の権威として評価を受けてきた。
本書が書かれた動機は、著者の序文にもあるように、ユダヤ系アメリカ市民として隣人のキリスト教徒の聖典を理解しようとしたところから出発して、同胞のユダヤ人に新約聖書を紹介するためであった。
本書の序文が詳しいのであらためて繰り返す必要はないが、本書は一般教養を有するレイマン(素人)向きに書かれた、どちらかといえば学問的色彩の強い書である。
キリスト教という信仰を推奨したり、あるいは逆に誹謗したりするためのものではない。
本書の初版が1956年であり、今から40年前の著作である。今日までの新約聖書学の進展が反映されていないのは、読者に不満が残るかもしれない。ただし、今世紀の50年代にすでに、ユダヤ人にとって伝統的に禁忌であったテーマに取り組んだ点を評価したい。
著者が改革派ユダヤ教のラビであるからこそ、キリスト教とユダヤ教の対話への突破口を開くことができたであろうと思う。
また、アメリカという宗教的寛容の土壌に生きるユダヤ教徒だから、オープンな心で新約聖書を読むことができたのかもしれない。今日、この分野に少なくないユダヤ人研究家が参加している現状を見るにつけ、一人の先駆者の最初の著作を日本に紹介することは意義があろうかと考える。
本書は、ユダヤ人がユダヤ人の立場から見た新約聖書の概観であるので日本の非キリスト者の読者には、本書はキリスト教の聖典の入門書として役立つかもしれない。
キリスト者には、自分の宗教の聖典について、異なった視点で、しかもユダヤ教的観点から振り返ってみる機会を提供するだろう。
ここで注意したいのは、本書はあくまでも学問的アプローチで新約聖書を客観的に展望しようとしていることである。
はたしてその目的が成功したかどうかの評価は、読む人の立場で異なるだろう。キリスト教各派が様々の神学的見解を抱くこの分野に関して、一冊の単行本にまとめることの困難と限界は著者がよく認識しているところである。
第二章に新約聖書への取り組み方を述べているが、著者の立場はアメリカのリベラルなプロテスタント神学の傾向をおびているようである。
「これから述べることは、こうした自由な学問の主流派の結論を良心的に描き出そうとするものである。したがって、本書でのアプローチは熱心な訓戒者のそれでも、擁護者のそれでもなく、反対者のそれでもない。むしろ厳正かつ正直な学問的な伝統を反映させ、真実を自由に探究してみたいと思っている。
こうしたリベラルなプロテスタントの伝統では、新約聖書をその時代の背景の中で、その原初の意味を追いながら、できるだけ正確に描き出すことを目的としている。この手法はまさに新約聖書を理解したいというユダヤ人にとって適切な方法である」(43頁)。
なお、本書で著者が新約聖書学の独自の研究結果を発表しているわけではない。以上のような前提を考慮すれば、いろいろの立場の読者も本書を読みつつ有益な知識を得られるものと信じる。
さて、キリスト教とユダヤ教との間には、この二千年間、迫害と対立という不幸な歴史があった。西欧の文化圏の渦中に暮らしながら、ユダヤ人がキリスト教についての知識を持つこと、特に新約聖書を読むことは長い間タブーであった。ユダヤ人がキリスト教について率直な見解を公表する例はまれであった。
一方、キリスト教の側もユダヤ教に対する、ステレオタイプの先入観と偏見に染まっていた。ところが、20世紀の後半、両者の対立の厚い壁が破られつつあり、和解と相互理解への道が少しずつ開かれていることはあまり知られていない。それについて少しふれてみたいと思う。
二つの宗教の関係に変化が現れたのは、第二次世界大戦以後のことである。この時期を前後して両者に影響を与えた大事件が起こった。それは反ユダヤ主義の頂点とも言うべき、ナチス・ドイツのホロコーストとユダヤ人国家、イスラエルの建国である。
まず、戦後に西洋キリスト教諸国にホロコーストを許したことへの罪意識が残ったが、キリスト教の反省はユダヤ教への対立から和解へ導くきっかけになった。
また、積極的にはドイツとのレジスタンスの戦いで、ユダヤ人とキリスト者の共闘が宗教の壁を乗り越えさせる一助となったという。その辺の事情を聖書学者アンドレ・シュラキの『ユダヤ思想』(119頁)から引用すると、「フランス文化世界のなかでのキリスト教徒とユダヤ教徒の出会いは、1940年から945年にわたるレジスタンスの戦いを通じて聖別された。
血の洗礼(一緒に戦ったこと)が、ユダヤ教徒とキリスト教徒の友情の礎石をゆるぎないものにした。……ユダヤ教に関してキリスト教側の教えてきたことを、歴史的に再検討するうごきが生じた。
セーリスベルグで開催されたユダヤ・キリスト教会議(1947年)によってさだめられた十項目は、第二ヴァチカン公会議ではっきりと認められた。
964年11月20日、金曜日、公会議の席上、反対九十九票に対する賛成1657票で、『ユダヤ教徒と非キリスト教者についての資料』が承認されたが、それは教会のユダヤ的起源を思い起こさせ、キリスト教徒とユダヤ教徒に共通な世襲財産の豊かさを強調し、両者が互いに知り合い尊敬し合うことを勧め励ますかたわら、ユダヤ教徒に対するこれまでの憎しみ、迫害、偏見(キリストを磔刑にしたことに対する非難をも含めて)を咎め、嘆かわしいものとみなし、あまつさえきびしく断罪するものである」
つまり、キリスト教の立場から(第二ヴァチカン公会議の宣言はカトリックのもので、必ずしも全教会の意思とは言えないが)、従来のユダヤ人にイエスの死の責任を追わせたことを撤回し、キリスト教のユダヤ起源を確認したのである。これは歴史的転換であると言えよう。
『福音書とユダヤ教』(1988年SCM Press, 邦訳ミルトス刊行)では、ユダヤ教とキリスト教の対話の実例として、お互いに相手の聖典の研究を共同で試みている。その本の序に、イエスの精神形成の跡を尋ねる旅として、キリスト教の信条の本質概念はユダヤ教の土壌で成長したこと、その土壌から根を抜かれると理解が出来なくなること、とのプロテスタント・キリスト教の理解が載せられている。両宗教の和解は新しい潮流として注目されてよい。
他方、イスラエル建国によりユダヤ人が離散の状況から二千年ぶりに自分の国をもったことは、宗教文化史的にも多大の意義をもつ。キリスト教文明の国における仮住まいから独立し、正統的ユダヤ教による民族結束の束縛から自由を得た結果、イスラエルにおいて従来のタブーを破る学問研究が始まった。(正統派はキリスト教文献にふれることをタブー視している)。
ユダヤ人学者による新約聖書研究もその一つで、ヘブライ大学のサフライ教授、フルッサル教授はじめ優れた聖書学、歴史学の研究者が登場している。
もちろん、ユダヤ教徒にとって新約聖書の研究は、第二神殿期ユダヤ教に関する情報を得ることが出発点であるが、原始キリスト教のユダヤ的背景を知る上でイスラエル学派が貴重な成果を挙げていることを、ついでに強調しておきたい。
近年、ユダヤ教徒とキリスト教徒の共同研究の組織「エルサレム学派」は、故R. Lindsey博士の指導下にユニークな共観福音書研究を進めている。
内容説明
ユダヤ人が聖書学の成果を踏まえて、キリスト教の聖典をヤダヤ人に紹介したユニークな書。
目次
第1部 聖書を読むまえに
第2部 パウロとパウロの手紙
第3部 共観福音書とイエス
第4部 そのほかの書
第5部 新約聖書の意義