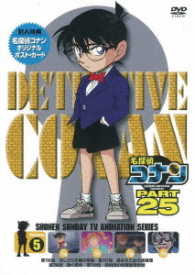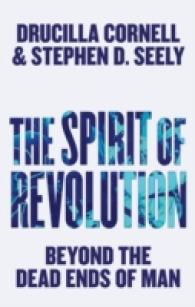内容説明
落語を楽しみながら江戸時代の庶民の「食生活」を知る。江戸時代の食べものや風俗を描いた資料性の高い当時の図版94点を収録。
目次
蕎麦(時そば―屋台そばのイ、ロ、ハ;そば清、そばの殿様―そばは喉で食うとか言いますが)
鮨(鮓、寿司)・五人まわし―江戸子だってねぇ鮨食いねぇというのは大坂鮨
鰻・鰻の幇間、素人鰻、子別―江戸の頃も今も御馳走であります
天麩羅・王子の狐―江戸風と言いますと、衣も厚く、味も濃い
お汁粉・御前汁粉―甘味処に付き合わされた辛党用にところてん
饅頭・饅頭こわい―甘い物をつまみに一杯なんて人も居ます
餅菓子・幾代餅、黄金餅、やかん、お節徳三郎の内花見小僧の部―和菓子の代表と言えばこれでしょう
菜っ葉・青菜、小噺―小松菜の本場は江戸川区小松川
おから(卯の花)・千早振る―もっと有効利用したいものであります
飯(小言(搗屋)幸兵衛、幾代餅―米、本来は完全栄養食品であります
阿武松、唐茄子屋政談、甲府い―腹が一杯になれば幸せであった時代もありました)〔ほか〕
著者等紹介
林秀年[ハヤシヒデトシ]
昭和24年疎開先の埼玉県浦和市生れ。昭和30年東京都渋谷区に転居。明治大学法学部卒業後平成16年まで信販会社に勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
偽教授
0
落語趣味の延長で読むにはいいのかもしれんが、食文化史の資料としては底が浅い2021/11/25
ふらい
0
落語のあらすじを中心に、現存する/していた店の話だの自分語りだのの話が続く本。ちょっと文章が素人臭く、落語以外の語りの部分も自分視点なところが多くてイマイチ。紹介してる落語の数は多いので、「あああったあったそんな話」という楽しみ方にはいいかも。2020/06/05
ダメカン
0
ふぐといえば「らくだ」でしょう。 2018/09/08
やわとしょ
0
落語のあらすじが多くて食べ物の話が期待したより少なかった。2019/08/07
-

- 洋書
- Howards End