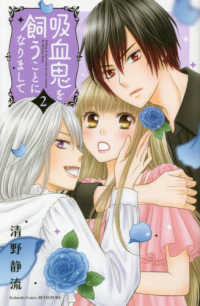内容説明
ボヘミア和協とは―近代チェコ民族主義成立への前史。19世紀において、いかにボヘミア貴族層とチェコ人中産階級が協力し、ハプスブルク帝国におけるボヘミアの自治を求めたかを考察する。
目次
第1章 一八七〇年代までのボヘミア国法運動の発展(伝統的なボヘミア国法;近代的なボヘミア国法理念 ほか)
第2章 ポトツキ内閣からホーエンヴァルト・シェフレ内閣へ(ポトツキ内閣の成立;ヘルフェルト会談とホーエンヴァルト ほか)
第3章 ボヘミア和協の交渉過程(和協交渉の開始;基本法に関する和協交渉 ほか)
第4章 ボヘミア和協の構造と新しいボヘミア国法(基本法の補足的な諸法案;新しい領邦条令 ほか)
第5章 ボヘミア和協の破滅的終焉(反和協運動のはじまり;第二の皇帝勅書の致命的効果)
結論(ボヘミア国法とボヘミア和協の意義)
著者等紹介
川村清夫[カワムラスガオ]
1958年生まれ。桐朋高校、上智大学文学部卒業。米国インディアナ大学大学院にて博士号(Ph.D)取得。専攻は東欧近代史。チェコ・ドイツ民族問題およびハプスブルク帝国の連邦化運動を研究する。湘南工科大学総合文化教育センター非常勤講師。東欧史研究会、ロシア・東欧学会、現代史研究会、比較文明学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん
4
墺洪帝国の内政問題を研究した本が日本語で出たということでとても興味があったのですが、やっとこさ読めました。始めは言語令やフェルディナント大公の三重帝国案も含めての内容かと思っていたのですが、実際はそれらの前史のようなお話でした。ボヘミア王国の独立と自治の問題がハンガリーとの課題と同じように同時並行的に展開していたことを初めて知りました。個人的に知りたい帝国の日常的な国内運営について知ることができる内容で、とても良い本でした。しかし、このテーマはもう少しおもしろく描けるような気がします。その点、残念です。2018/05/03
-

- 和書
- なっとくする電気回路