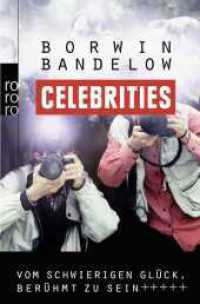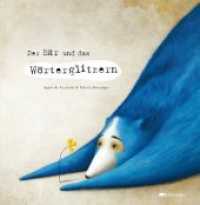内容説明
公共に開かれた図書館を持たない先進国など一つもない。しかし、日本ではその姿が大きく変貌してきている。戦後の設立過程から現在の混迷状況までの過程をつぶさに描き、図書館問題の本質を論じる。
目次
第1部 戦後期公共図書館史の歪曲と真相(語られた歴史と不都合な事実;占領期の民主化政策と出遅れた公立図書館;ささやかな図書館法と肥大化した後付け解釈;なけなしの職業資格と図書館発展への抵抗)
第2部 粉職された図書館発展と用意された顛末(神話の中の『中小レポート』と日野市立図書館;図書館発展の実態と好都合な共同幻想;図書館界のハリネズミ化と自滅への道;最後の助け舟と泥舟への固執)
著者等紹介
薬師院仁志[ヤクシインヒトシ]
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程(教育社会学)中退。京都大学教育学部助手、帝塚山学院大学文学部専任講師等を経て、同大学教授(社会学)、大阪市政調査会理事、レンヌ第二大学レンヌ日本文化研究センター副所長
薬師院はるみ[ヤクシインハルミ]
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程(図書館情報学)研究指導認定退学。金城学院大学文学部専任講師等を経て、同大学教授(図書館情報学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
21
何度も登場する前川恒雄氏の講演を聞いたことがあるが、高齢にもかかわらず図書館への熱い想いを語っておられ、司書さんたちの心を掴んでいた。前川氏が館長を務められた日野市立図書館の躍進史について、本書でくわしく分析されているが、豊富な予算、60年代の人口増加など、様々な好条件が重なったレアケースであったことが分かる。これを神話化し全国自治体の公立図書館の目標にしてしまったことが、悲劇の始まりだった。貸出こそが図書館サービスであるいう認識を改め、今こそ公共図書館の真の目的とは何かを考え直す時期だと思う。2020/09/04
軍縮地球市民shinshin
20
注が881個もついているので学術書なのだろう。戦後図書館史の通説を根底から覆す本である。戦後の公共図書館はGHQの一部局CIEによる「日本民主化政策」の一環として開始される。それが1950年の図書館法成立に至り、戦前の「国家主義的図書館」から戦後の「民主的図書館」に「生まれ変わった」というのが通説なのだが、そもそも本書はGHQは日本の公共図書館にさほど関心はなく、自ら日本各地に設置していたCIE図書館によって民主主義を広げるだけで良いと考えていたようだ。だが図書館担当官キーニーは個人的に図書館法成立に多大2020/08/05
やまやま
16
国においてユニバーサルなサービスと地方分権の関係は費用負担の問題がまずは代表格で、例えば沖縄の基地の問題などを思い浮かべると、国防というユニバーサルな命題と具体的な立地というトレードオフは正解がない。ただ、一歩踏み出すと、お金で解決できる部分があれば、活用を検討すべきであろう。さて、図書館について、戦後史の中で中央図書館制度のようなユニバーサルな計画が立案されたが実現せず、立法としては地方分権的な図書館法が定められたことを端に、原因を関係者の内部力学で説明しようとする試みが本書といえるだろうか。2021/01/13
K
6
(20200518,016.21)界隈の偉い人や日野図書館神話をぶった切る本。なんで全体的に左寄りなのか、なんで無料なのか、なんで非正規の官製ワーキングプア・やりがい搾取が目立つのかよくわかった。司書職の「専門・専門性・専門的」にこだわる彼らのプライドの高さが謎だったが、それも氷解。こんなグダグダだから、門外漢の私でも50で半年で家で資格を取り就職できるのだ。待遇の悪さを「国が悪い」と毒づく図書館職員にぜひおすすめ。ただし、司書資格勉強中に絶対に読んではいけない本。テキストが嘘くさくて、やってらんなくなる2020/07/09
ことうみ
4
図書館=無料で好きな本が借りられる。 貸出数増やさないと存在意義が保てない。 だから、漫画や住民の要望が多いポピュラー本を置く。 専門書だから難しいし同じことの繰り返しや引用を載せて頁数稼いでる感じ。 戦後のGHQが日本の図書館振興に関心持ってくれなかったことと、日野市の図書館がパイオニアなことと有松氏とキー二ー氏が色々奮闘したのは分かった。2020/12/27