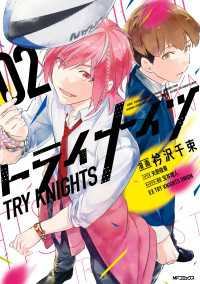目次
1 アイデンティティと持続可能性(ここはどこ?―日本の都市再開発の風景の印象から;グローバル化の風景 ほか)
2 スイスの産業施設跡地の再開発(ウィンタートゥール市ズルツァアレアル;チューリヒ市ノイ・エリコン地区 ほか)
3 日本の産業施設跡地の再開発(関東周辺の産業施設跡地の都市再開発の事例;行政の再開発担当職員に聞く アイデンティティと持続可能性)
4 アイデンティティと持続可能性に関する議論(エリアマネジメントは持続可能性を高めるか?―EU補助プログラムUPP/URBANに学ぶ;都市計画行政の立場から―チューリヒ市副都市計画局長ペーター・ノーザー氏に聞く ほか)
5 まとめ―迎える危機とアイデンティティ(迎える危機とアイデンティティ)
著者等紹介
木下勇[キノシタイサム]
千葉大学大学院園芸学研究科・教授。工学博士(1984年)。専門は、都市計画・農村計画。1978年、東京工業大学建築学科卒業。1979‐80年、スイス連邦工科大学留学。1984年、東京工業大学大学院博士課程修了。農村生活総合センター研究員、千葉大学園芸学部助手、助教授を経て、2005年より現職。「三世代遊び場マップ」はじめ、ワークショップ手法で、子ども・住民参画のまちづくりを展開し、傍ら再開発の研究を進めてきた
ビンダー,ハンス[ビンダー,ハンス][Binder,Hans]
建築家。スイス・ベルン応用科学大学ブルグドルフ校(建築・木質・建設学部)教授。専門は、都市計画および建築理論。スイス連邦工科大学にて建築を学び(1982‐1988)、米国ハーバード大学GSD受講後にボストンにて実務経験。その後、スイスに戻り、ヴィンタートゥールにて建築事務所Binder Architektur AGを開設。1992年より現職。大学にて都市計画のポストドクターコースを設け、ドレスデンやパリなどの大学の客員教授も務める
岡部明子[オカベアキコ]
建築家。千葉大学大学院工学研究科准教授。環境学博士(2005年)。東京生まれ。1985年、東京大学工学部建築学科卒業後、1987年まで磯崎新アトリエ(バルセロナ)に勤務。その後、日本に戻り、1989年、東京大学大学院建築学専攻修士課程を修了し、再びバルセロナへ。1990年、堀正人とHori & Okabe,architectsを設立、建築などのデザインを手がける。1996年より東京(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。