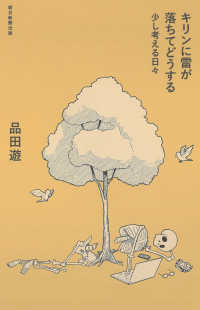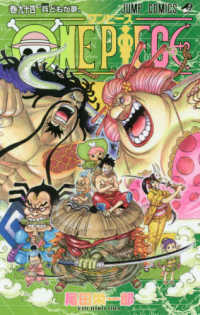内容説明
言語と植民地主義の複雑な関係!いかにしてズールー語学習はアパルトヘイトに組み込まれていったのか。留学を機に著者がはまってしまった設問だ。学習経験から日常の対話での気づき、そして文学や歴史まで、ズールー語を取り巻くエピソード満載の入門書。
目次
1 ズールー語学習という経験(ズールー語学習者の一日;ズールー語で挨拶する)
2 植民地化とズールー語(宣教とズールー語学習教材の出版;アフリカ人統治行政と白人のズールー語話者;スチュアートの歴史教科書)
3 民族語としてのズールー語(ニャンベジの苦闘;ニャンベジの達成;なぜこんなにも拍手が多いのだろうか?)
著者等紹介
上林朋広[カンバヤシトモヒロ]
1986年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻博士課程修了。博士(社会学)。一橋大学大学院社会学研究科特任講師(ジュニア・フェロー)を経て、現在日本学術振興会特別研究員CPD(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つまみ食い
9
アフリカ史などを研究しながらズールー語を学習する著者の言語学習の体験を導入に、白人による支配と複雑な関係を持つズールー語の歴史を解説。最近では南アフリカにおける外国出身のアフリカ人の排斥にも利用されている側面もあるようだが、ズールー語話者によるズールー語文学や言語研究の試みのこれまでと可能性についても触れられている。70ページにも満たないのに密度が高い。2025/01/21
samandabadra
2
アパルトヘイト時代の南アフリカの言語政策に関してはThe multilingual university(Mbulungeni Madiba)という論文やジョナサン・ヘイスロップの『アパルトヘイト教育史』でも言及されている。植民地時代の言語政策が継続されたような、最新の知識の獲得を阻害するため宗主国の言語(=英語、仏語)は教えないという方針であったが、終了後の教育に関してはこの本である程度のことが分かる。なにより、今もかつてのような子供の教育向けの文学しかないことは何とかせねばならないだろう。2025/03/28