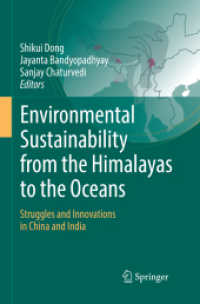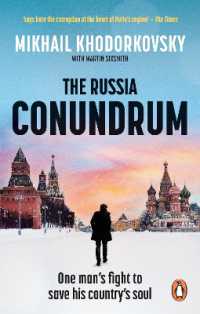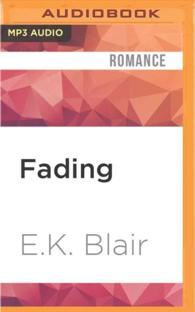内容説明
白い馬は射殺されたのではなかった!?小学校国語教科書にも登場する「スーホの白い馬」。子供たちに親しまれている「民話」の誕生秘話。モンゴルの馬頭琴起源伝説「フフー・ナムジル」や中国創作文学「馬頭琴」と対比しながら、経過と背景をたどり、馬を愛するモンゴル人の文化とモンゴル草原に憧れる日本人の心の歴史に触れる。
目次
第1部 日本における「スーホの白い馬」の受容(「スーホの白い馬」の始原を探る;日本人のモンゴル草原への憧れの産物としての「スーホの白い馬」)
第2部 中国による「スーホの白い馬」の改編(「階級闘争」にすりかえられた中国語版「馬頭琴」;共産党政権や市場経済下における内モンゴルの文芸作品―中国語版「馬頭琴」と対比して)
第3部 「スーホの白い馬」に垣間みるモンゴル文化(民族楽器としての馬頭琴の「誕生物語」;「スーホの白い馬」にみられる文化的教育論)
第4部 「スーホの白い馬」の故郷はいま(「スーホの白い馬」の故郷から―黄砂の発祥地として知られた「モンゴル」)
著者等紹介
ミンガド・ボラグ[ミンガドボラグ]
1974年、内モンゴル自治区シリンゴル生まれ。1995年、教員養成学校であるシリンゴル盟蒙古師範学校を卒業、小学校・幼稚園で教員として働く。1999年に来日、日本語学校を経て2001年に関西学院大学文学部に入学。2011年、関西学院大学教育学研究科博士課程後期課程修了。博士(教育学)。現在:関西学院大学教育学部非常勤講師。翻訳・通訳として働く傍ら馬頭琴奏者としても活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KEI
とよぽん
チェアー
ののまる
風に吹かれて