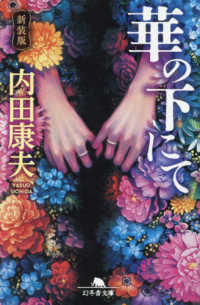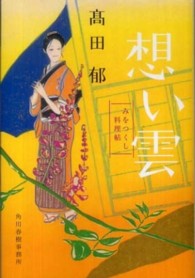目次
テクストを分析的に読むために
ロシア・フォルマリズム ウォーミング・アップ―夏目漱石『夢十夜』「第一夜」
知足と安楽死を超えて―森鴎外「高瀬舟」1
焦点化、直接話法 語ること・見ることとテクストの仕組み―森鴎外「高瀬舟」2
単起法、括復法、聞き手、空所 謎と反復をめぐるテクストの仕組み―森鴎外「高瀬舟」3
“奇蹟”の読み方/読まれ方―芥川龍之介「南京の基督」1
語りの時間、錯時法 語り手はどこにいるのか―芥川龍之介「南京の基督」2
語りの時間、入れ子構造、焦点化 奇生する語り手の欲望―芥川龍之介「南京の基督」3
“名作”が名作になるまで―川端康成「伊豆の踊子」1
持続、休止法、要約法、情景法、省略法 偽装された“現在”―川端康成「伊豆の踊子」2〔ほか〕
著者等紹介
松本和也[マツモトカツヤ]
神奈川大学外国語学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
梶
28
良書。芥川「南京の基督」、康成「伊豆の踊子」、岡本かの子「老妓抄」、太宰「桜桃」など、短編を中心に、ポイントを絞って読解してゆく集成。中でも第15章の斎藤理生先生の筆が冴えている。ジュネットの物語論を大まかに知悉することもでき、テクスト分析の入門として、大学一年生が遍く読むべき一冊であろう。2025/03/01
masabi
12
【概要】テキスト分析を理論と実践を通して解説する。【感想】テキスト分析とは、小説がいかに書かれているかに着目し、テキストの記述を根拠に客観的に論述することとまとめられる。題材の短編が巻末にあり、適宜内容を確認できて便利だ。各作品の成立史や文豪の簡潔な説明、位置付けなど作品外の情報もある。一番興味深かったのは、「南京の基督」だ。合理と信仰の対立、格差以外に少女が情報をコントロールし、望ましい印象を巧妙に植え付けているとの見方は少女を下に見る語り手を手玉に取るようで鮮烈だった。2020/08/02
しんえい
11
「いかに書かれているか」という切り口から物語を考える。語り手の位置や意図、語りの水準。焦点化。頻度や持続、語りの時間と錯時法。空所=謎。このような理論を、どこまで教室に持ち込むのか。これらの理論を持ち込んだ先に何があるのか。2020/05/06
ロラン
8
日本の近代文学をテ「ク」ストとして、分析的に読解する方法を学ぶ、入門的なテ「キ」ストとなっています。アンソロジー形式で、読んでいて飽きがこない趣向なのが、嬉しいポイントですね。テクストは珠玉の短編集(夢十夜、高瀬船、南京の基督、伊豆の踊子、老妓抄、桜桃)でもあり、巻末に本文全文が掲載されているという親切ぶりです。そして更なる親切仕様として、同一作品を作家論とテクスト分析のそれぞれ1章を設けて分析しているため、作家論と対比してのテクスト分析の視点が、より分かりやすくなる体裁になっています。2018/10/30
たく
7
テクストを分析的に読む、というのがどういう事なのかパッと考えて分からなかったので読んでみた。文章の内容自体ではなく語りの技法を中心に解析していく内容は文豪の作品がなぜ評価されているかなどが分かり、また物語の構造を理解する手助けにもなりそうだった。 ナラトロジーについてもっと学びたくなる1冊。2022/02/06