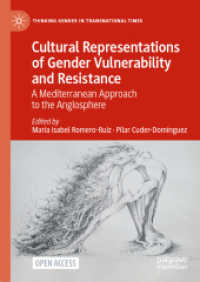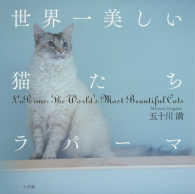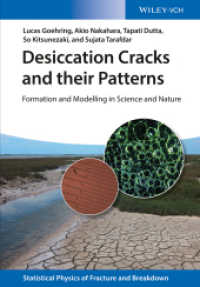出版社内容情報
ソフトウェア開発の古びたやり方を刷新し、チームに活気と信頼、そして成功を与えるXP(エクストリームプログラミング)。その「XP入門」が初版より5年の歳月をへて、新たに生まれ変わりました。提唱者ケント・ベックにより、すべてが書き改められています。XPがいかなる進化をとげたのか、ぜひお確かめください。
目次
第1部 XPの探究(運転の心得;価値、原則、プラクティス;価値;原則;プラクティス ほか)
第2部 XPの哲学(起源のストーリー;テイラー主義とソフトウェア;トヨタ生産方式;XPの適用;純度 ほか)
著者等紹介
長瀬嘉秀[ナガセヨシヒデ]
1986年東京理科大学理学部応用数学科卒業。朝日新聞を経て、1989年テクノロジックアートを設立。OSF(Open Software Foundation)のテクニカルコンサルタントとしてDCE関連のオープンシステムの推進を行う。OSF日本ベンダ協議会DCE技術検討委員会の主査をつとめる。現在、株式会社テクノロジックアート代表取締役。UMLによるオブジェクト指向セミナーの講師、UML関連のコンサルティングを行っている。UML Profile for EDOCの共同提案者、ISO/IECJTC1 SC32/WG2委員、電子商取引推進協議会(ECOM)XML/EDI標準化調査委員。明星大学情報学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
55
XPはあたりまえのことを極端に表現しているだけかも。eXtreme Presentation。presentationかprogrammingかそんなことはどっちでもよい。自分のやっていることを本の中に見つけると共感できる。ソフトウェア工学という名目の本に、抽象論ばかり書いてあったり、制約条件を書かずに特定の場合しか成立しないような例が書いてあっても嬉しくない。例えば、落水「water fall」。自分が実際にやっていることとが本の中に書いてあると安心して読める。2014/04/01
紙魚
3
読んだつもりになっていたが、積読タワーから発掘されたので改めて読んで見る。XPにはどんな実践があるのかの概要を説明しているだけで、実際どうやって行っていくかの具体的な話はあまりない。全体的にソフトウェア開発プロジェクトそのもの(そして関係者たちの人間関係を)をより良くしていくためのコツの寄せ集めといった気楽さがある気がする。2018/06/13
まも
2
XPといえば、残業しないとかペアプログラミングとか、短い期間でリリースをイテレートするとか言われていて、それらを実践すればXP開発であると思われがちだけど、XPの本家である本書を読むと、それらを実践する環境はどうあるべきかを考え、構築していくのがXPなんだと思えた。ペアプロをするには密なコミュニケーションをとらないといけないし、短い期間でリリースしていくにはシンプルな設計をして、ユーザーにとって重要な機能を洗い出せないといけないのだ。2012/04/26
Kitamuu
1
コミュニケーション、シンプルさ、フィードバック、勇気、尊重という5つの価値。 XPでは改善することでソフトウェア開発における優位性を維持する。今日できる最良のことを行い、認識することを目指して努力し、明日さらに向上させるために必要なことをりかいするのがXPでのサイクルである。 成功するのが困難な場合、失敗すればよい。失敗は無駄なことだろうか。知識を与える場合は無駄ではない。行うべきことがわからないときには、あえて失敗することが成功への最短で確実な道になる場合がある。 2021/03/24
Luo Yang
1
古典とか言われがちな本ですが、十分実用的です。出版から10年以上経った今でも、(残念ながら)基本的な課題は何も変わらないように思います(組織にもよるのでしょうが)。XPの価値、原則、そしてプラクティスを少しずつ取り入れ、日々の開発をよくしていこうという思いを新たにしました。ちなみにテクノロジックアートの訳にしては珍しく、訳がまともな部分が多いです。2012/04/22