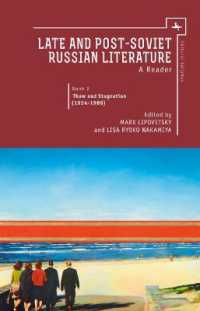出版社内容情報
いまだアクチュアリティを放つ、そのファシズム論、国家論、自由論!
人文学的伝統を守り抜いたイタリアの巨人。
初の本格的クローチェ論。
単なる政治的判断ではなく、西洋の人文学的伝統に裏打ちされた知のあり方そのものにおいて、ファシズムに抗し得たクローチェ。学問を細分化するだけの大学 アカデミズムにも、大衆煽動的ナショナリズムに便乗するだけのジャーナリズムにも依存せず、「知」と「学問」の自律性と全体性を守り抜いたその思想は、今 日の我々に何を示唆するか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やまやま
9
著者の博士論文等を加筆再編したとのことであるが、学術一辺倒でなく、読み物としてクローチェの人物像をよく伝えていると感じた。自由な思索を最も重要な価値観とするクローチェは、政治を含む日常は秩序だっていることを望み、そのためファシズムも次善の策としては受け入れることのできるものであった。しかし、次第に自由な思索そのものが秩序の名のもとに制限されるに至り、政治が文化を汚染することを嫌い、一転してファシズムに反対を表明した。その歴史観は、個人が道徳活動を行う契機から思想が発展していくという観念論であった。2020/10/29
てれまこし
6
クローチェは欧州では独自の哲学体系を築いた巨人だが、日本での知名度はいま一つで、邦訳も歴史学関連(と美学)に限られる。反ファシズムの関心から政治論集も訳されてるけど、哲学体系に関する本が未訳で、この哲学が歴史作品やファシズム批判などとどういう関係にあるのかよくわからない。だから実際に原文を読んだ人の話を聞いてみるしかないが、これを読んでもやっぱりわかった気がしない。反ファシズムに転ずることで知的盟友であり親友であったジェンティーレや弟子たちと訣別することになったというドラマつきだから、思想史的に気になる。2023/04/17
Mentyu
3
クローチェが日本で言うところの柳田国男的ポジションにいたことがよく分かった。在野で活躍しながら政界にも進出している点などそっくり。総合的な学問体系の構築を目指していたということなので、単純に歴史家と割りきれないところも興味深い。実証主義へ対する批判的態度も歴史学だけの話だと思ってたのだけど、人文社会科学全体に向けたものだったとのこと。こういう在野の化け物は、専門分化の進んだ現在ではもう出てこないんだろうな。2019/03/11
greenman
2
本書はイタリアの歴史家、哲学者ベネディクト・クローチェの伝記でありながらも、彼の思想を分析した研究書。クローチェは日本ではほとんど知られないイタリア人の歴史家や哲学者(そもそもイタリア人の学者自体が知られていない)だけど、大学でアカデミズムを学びながらも大学のアカデミズムに失望し、大学外での活動を一生行った。クローチェの自由主義はロック、ルソー、ベンサム、ミルとは異なり、ヘーゲルの観念論を元にした「善」の追求(芸術・学問・政治・経済活動)に集中することで達成し得るものと考えた。自由を考えなおすのにオススメ2012/12/12