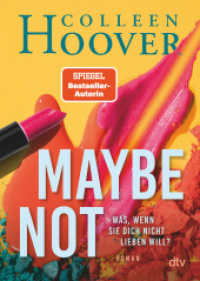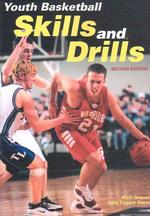内容説明
バブル期の狂乱の「美術ブーム」とは、一体何だったのか!?バブル後の著しい市場の縮小の時代から現在までの美術市場を徹底分析。美術との関わりから、個人/国家/企業と文化のあるべき姿を模索。
目次
第1章 バブル崩壊とその後の日本市場
第2章 国際市場と価格の動向
第3章 日本・美術商の業績
第4章 企業と美術
第5章 国家・地方・美術館の問題
第6章 欧米・東アジアの文化状況
第7章 混迷から激変へ―二〇〇七年の状況
第8章 第二次バブルの推移と今後―二〇〇八年の状況
著者等紹介
瀬木慎一[セギシンイチ]
1931年、東京に生まれる。美術評論家。1977年以来、総合美術研究所所長。1953年から美術評論に携わり、主として近・現代美術および美術社会学を専門とし、欧米、アジアにわたって活動する。多摩美術大学、和光大学、慶應義塾大学、東京藝術大学などで教える。全国各地の美術館の役員を務め、現在、池田20世紀美術館などの役員、岡本太郎美術館協議会会長。国際美術評論家連盟会員、日仏美術学会会員、ジャポニズム学会会員。国際浮世絵学会、伝統木版画技術保存財団などの役員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。