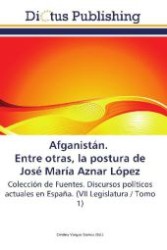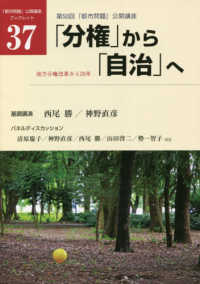内容説明
西洋文明の根幹は「身体」にある。ミシュレ、モース、エリアス、アドルノ、フーコー、ブロックなど、従来の身体史の成果と限界を鮮やかに呈示し、「他のいかなる時代よりも現在の原型である」中世の重要性を説く。「身体」に多大な関心を示し、これを称揚すると同時に抑圧した、西洋中世キリスト教文明のダイナミズムの核心に迫る。大好評『中世とは何か』に続く、待望の第2弾。
目次
序 身体史の先駆者たち
1 四旬節と謝肉祭の闘い―西洋のダイナミズム
2 生と死
3 身体の文明化
4 メタファーとしての身体
結び ゆるやかな歴史
著者等紹介
ル=ゴフ,ジャック[ルゴフ,ジャック][Le Goff,Jacques]
中世史家、『アナール』編集委員。1924年、南仏のトゥーロン生まれ。青年時代を第二次大戦の戦火の中で過ごしたのち、高等師範学校に進学。在学中、プラハのカレル大学に留学。1950年、高等教育教授資格試験に合格。このときブローデルやモーリス・ロンバールが審査委員を務め、これがアナール派の歴史家たちに出会う最初の機会となる。以後、ソルボンヌのシャルル=エドモン・ペランの指導下で博士論文を準備するかたわら、アミアンのリセ、国立科学研究所、リール大学文学部にポストを得、またこの間、オックスフォード大学リンカーン・カレッジ、ローマ・フランス学院へ留学。1959年、アナール派が中心となって組織される高等研究院第六部門に入り、以後、フェーヴル、プロック、ブローデルらのあとを受け、アナール派第三世代のリーダーとして活躍。1969年、ブローデルのあとを受けて、エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ、マルク・フェローとともに『アナール』誌の編集責任者となる。1972年、ブローデルの後任として第六部門部長となる。1975年、高等研究院第六部門の社会科学高等研究院としての独立に尽力
池田健二[イケダケンジ]
1953年広島県生まれ。上智大学外国語学部講師。フランス中世史・中世美術史専攻
菅沼潤[スガヌマジュン]
1965年東京都生まれ。フランス近代文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
左手爆弾
児玉
すがし
更新停止中
刻猫