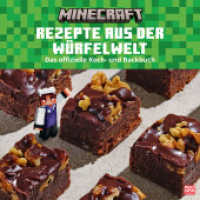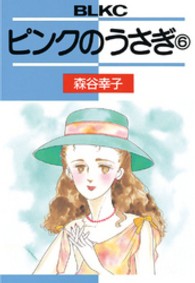内容説明
時は1870年8月16日午後2時、舞台は第三共和政前夜のフランスの片田舎。定期市が今やたけなわである。…普仏戦争における最初の敗北の報せが届くと、噂の交錯、政治に関する表象の単純さ、昔の秩序と過去の災厄がよみがえるのではないかという強迫観念、そして君主ナポレオン三世に対する愛情などの諸要因があいまって、農民たちは奇妙で名状しがたく耐えがたい残虐行為にはしることになる。突然、群衆によって捕らえられた一人の青年貴族アラン・ド・モネイス。弱々しくて若禿げの、いかにも見栄えのしない32歳になるこの独身男は、「共和国万歳!」と叫んだという嫌疑をかけられて、二時間にわたる拷問を受けた挙げ句、村の広場で火あぶりにされた。農民の怒りが引き起こした虐殺事件としては、フランス最後のものとなったこの事件とは一体何であったのか?著者は「人喰いの村」の事件に、「群衆の暴力と虐殺の論理」「集合的感性の変遷」という主題を立てて精密な解読を施してゆく。
目次
第1章 感情の一貫性
第2章 不安と噂
第3章 虐殺の歓喜
第4章 呆然自失する化け物たち
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
10
この事件から日本人は、関東大震災の後に起きた虐殺事件を思い起こさなければならない。 詳しくは、『9月、東京の路上で』をお読みいただくとして、事件の後に褒章を求める無邪気さは、同じ様な心理があったのだろう。 「アノ当時の状態としてアレ丈の事に気づいたのは寧ろよい事をしたとさへ思っている」(埼玉県内務部長。山岸秀『関東大震災と朝鮮人虐殺』) 2022/05/05
ヤヨネッタ
0
虐殺のスキャンダル性は、流血から生まれるというよりも、秩序やシステムの完全な不在の中で死体が即座に生み出されるところから生じる。164p 1870年8月16日午後2時、不運な青年貴族が2時間にわたる拷問の末に火あぶりにされた事件を読み解く。数十年前なら当たり前だった残酷さが1870年には時代錯誤の過去の化け物として社会から完全に否定される。この本は19世紀の遠い過去の事件を扱っているが、ネットで対立や断絶が広く可視化されて誰もが誰かの敵となりうる現代で自分が何者か考える時に示唆を与えてくれるかもしれない。2019/10/18
Arte
0
19世紀フランスの田舎の村で、市にやって来た貴族の青年が突然村人達に暴行されて焼かれた事件の背景をつらつらと書いた本。フランスの農民は、貴族と司祭と共和制が敵で、基本的に皇帝支持っぽい。フランス革命で散々野蛮なことが横行していたが(緊張を和らげ、苦難の時期の後で集団の調和を回復することも虐殺の機能)、19世紀に入ると、虐殺の際に作動する理解できない盲目的な諸力を解放することは許容し難いこと、淫らなことになった、らしい。2025/01/26
Cebecibaşı
0
横綱相撲という感じの社会史研究。19世紀に発生した虐殺事件が発生した原因を当時の社会状況とそれに伴う民衆心理を巧みにすくい上げていくことで復元していく非常に面白い本だった。この本を読んで色々連想するところはあるものの、すぐに現代日本の状況に短絡的に読み換えるよりも、どのようにして虐殺を行った集団の心理が形成されたのかを考えながら読む方がいいだろう。2020/01/30