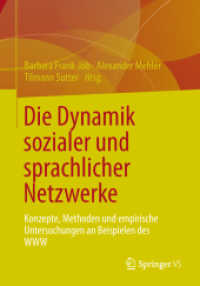内容説明
今、理科教育では、子どもが基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力などの能力を獲得することが急務となっています。このため、教師は、子どもに、どのようにして基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力などの能力を育成していくかが大きな課題となっています。小学校新学習指導要領改訂のポイントと授業改善の方法がわかる。
目次
第1章 新理科授業づくりのポイント(新しい理科で育てたい力;理科で育てるべき力を育成する授業;授業構成のためのポイント)
第2章 各学年の授業展開(第3学年(物と重さ;風やゴムの働き;光の性質;磁石の性質;電気の通り道;昆虫の成長;昆虫の体のつくり;植物の成長と体のつくり;身近な自然の観察;太陽と地面の様子)
第4学年(空気と水の性質;温度と体積の変化;温まりかたのちがい;水の三態変化;電気の働き;人の体のつくりと運動;季節と生物(1年間)
天気の様子
水の自然蒸発と結露
月と星)
第5学年(物の溶け方;振り子の運動;電流の働き;植物の発芽と成長;植物の結実;魚の誕生;人の誕生;流水の働き;天気の変化)
第6学年(燃焼のしくみ;水溶液の性質;てこの規則性;電気の利用;人の体のつくりと働き;植物の養分と水の通り道;生物と環境;土地のつくりと変化;月と太陽))
資料編(新学習指導要領小学校理科全文;新しい理科の目標と内容;理科におけるメタ認知;小学校理科における個に応じた指導のあり方;学校放送の活用;理科におけるインターネットの活用;科学館・大学・企業等との連携)
著者等紹介
角屋重樹[カドヤシゲキ]
1949年三重県生まれ。広島大学大学院教育学研究科教科教育学(理科教育)専攻博士課程単位取得退学。博士(教育学)。広島大学教育学部助手、宮崎大学教育学部助教授、文部省初等中等教育局教科調査官を経て、広島大学大学院教育学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。