目次
何故「思想史で読む史学概論」なのか
歴史を学ぶにあたり
徳川時代の歴史書の様式(王朝史)
一国史としての日本史の特質
日本はどのように語られるのか―その「作法」
「世界史」という言説
マルクス主義歴史学
現代の世界史理論
トランスナショナル・ヒストリーという視座
近代実証主義が問えないもの―植民地朝鮮における歴史書編纂
現代日本のナショナリズムと「教科書問題」
わたくしの問題意識の来歴
著者等紹介
桂島宣弘[カツラジマノブヒロ]
1953年生。立命館大学文学部教授。日本思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
16
高校歴史教育において歴史学を扱う必要を強く感じる今日この頃。著者の専門は私と同じく近世日本思想史であるので関心のある範囲も近く、学ぶ所が多かった。歴史学概論(1章)、歴史学の歴史(2〜8章)、日本植民地の朝鮮史(9章)、教科書問題(10章)に、著者の思想遍歴(補論)と子安、安丸、丸山についてのコラムという構成。歴史研究、叙述の難しさを実感する。歴史総合が必修化するにあたり、トランスナショナルヒストリーの視座と、東アジアの歴史認識問題についての意識は必須であると思った。2020/03/22
さとうしん
12
日本思想史専攻の研究者による史学概論。近現代の一国史が固有性を求めるのに対し、前近代の王朝史が共通性・普遍性を意識していたこと、秀吉の朝鮮出兵について民族主義的な視点が支配的だったはずの韓国から却ってトランスナショナル・ヒストリー的な研究が出てきていること、植民地時代の『朝鮮史』の編纂をめぐって、たとえ実証主義的、学術的であっても、ひとたび「正史」として編纂されることで、現地の人々の多様な歴史や視線を抑圧・隠蔽する権力として作用するという議論を面白く読んだ。2019/08/09
浅香山三郎
8
日本の近世の民衆思想や、幕末期の宗教運動を中心に研究されてきた思想史家が、それと密接な関係にある史学概論をまとめたもの。それゆへ、テクストのもつ思想性とイデオロギー性に意識的に向き合ひ、歴史の「事実」が選択・配列されてゐるといふことの諸矛盾・諸問題に重点がおかれ、史学史的な腑分けを通じて諸時代の歴史意識にも踏み込む。問ひを立てる主体としての自分自身にも言及した「補論 わたくしの問題意識の来歴」も興味深い。2022/08/04
-
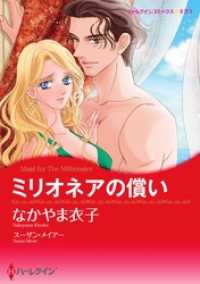
- 電子書籍
- ミリオネアの償い【分冊】 7巻 ハーレ…
-
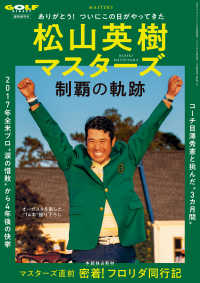
- 電子書籍
- ゴルフダイジェスト 2021年6月号臨…
-
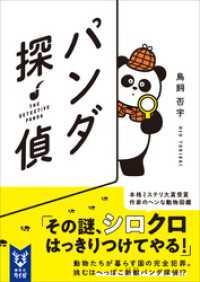
- 電子書籍
- パンダ探偵 講談社タイガ
-
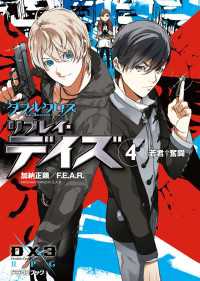
- 電子書籍
- ダブルクロス The 3rd Edit…
-
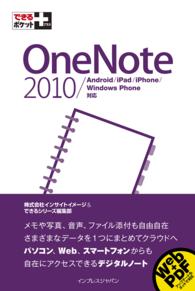
- 電子書籍
- OneNote - 2010/Andr…




