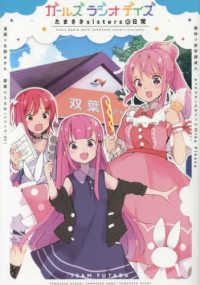内容説明
環境汚染型流域社会から環境保全型流域社会へ。「山」から「川・海」まで、農業者と漁業者、流域の地域住民が手を結ぶ、著者提唱の「流域共同管理」による実践的流域社会論の展開とは。「限界集落」概念提唱の初出論文(1988年)も収録。
目次
序章 現代における流域社会研究の課題
第1章 山村の高齢化と限界集落
第2章 現代山村にみる“人間と自然”の貧困化
第3章 農山村の集落構造と流域社会
第4章 山村の活性化と環境保全―流域社会の連携をめざして
第5章 「山」の荒廃と流域環境の保全―四万十川、そして千曲川へ
第6章 今なぜ山・川・海なのか―流域の共同管理による地域の再生
第7章 網走川流域における農業・漁業の連携と流域共同管理
第8章 現代山村の危機的状況と地域の再生
著者等紹介
大野晃[オオノアキラ]
1940年生まれ。旭川大学大学院教授。高知大学教授、北見工業大学教授、長野大学教授を経て2013年から現職。高知大学名誉教授。千曲川流域学会会長、日本村落研究学会副会長、日本農業法学会理事などを歴任。専門は環境社会学、地域社会学。日本全国の山村地域のほかルーマニア、スウェーデンなどの条件不利地域の比較研究、村落研究を続ける。綿密なフィールドワークを経て1988年に「限界集落」の概念を提唱。四万十川流域や吉野川流域などの研究成果をふまえた「流域共同管理論」も唱える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。