内容説明
舞台は16世紀の大航海時代、見果てぬインディアスを夢見て船に乗り込んだ「私」が上陸したのは食人インディアンたちが住む土地だった。「私」は独り捕らえられ、太古から息づく生活を営む彼らと共に過ごしながら、存在を揺るがす体験をすることになる…。無から生まれ、親もなく、名前もない、この世の孤児となった語り手を通して、現実と夢幻の狭間で揺れる存在の儚さを、ボルヘス以後のアルゼンチン文学を代表する作家が描き出す破格の物語。
著者等紹介
サエール,フアン・ホセ[サエール,フアンホセ] [Saer,Juan Jos´e]
1937年、アルゼンチンのサンタフェ州セロディーノにシリア系移民の息子として生まれる。1959年、ロサリオ大学で哲学を専攻するものの中退、以後雑誌などの仕事をこなしながら創作に従事する。1968年、「ヌーヴォー・ロマン」研究の名目で奨学金を得てパリへ渡り、以後フランスに定住。創作活動の傍ら、1971年からはレンヌ大学で文学を講義した。2005年、パリに没する
寺尾隆吉[テラオリュウキチ]
1971年、愛知県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。現在、フェリス女学院大学国際交流学部准教授。専攻、現代ラテンアメリカ文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fishdeleuze
23
非常に素晴らしい。だが、正直うまく消化できていない。読んで中に入ったものをテキストとして外に出す準備ができていない。まだ胸から腹のあいだになにやら塊がうごめいている感じがする。サエールは、アルゼンチンにおいては、ボルヘス、コルサタルと並ぶ代表的な作家の一人で、未邦訳の重鎮ともいわれていたが、本国においてはいわゆる玄人好みの作家といった存在で、(ピグリアやジョサ(リョサ)、フエンテスらの後押しもあり)広く社会に認知されたのは90年代になってからだという。→2016/02/11
長谷川透
23
見習い水夫だった主人公は冒険の中でインディオの襲撃に遇い、船隊長を殺害され、自らは囚われの身となる。原住民の村で目撃したのは、人肉喰、乱交、乱痴気騒ぎなどの蛮行、日常の奇異。野蛮人の全ての行動は、解体、解放に結びつくと主人公は考え付くが、その行動原理も結局は快楽に結びつけるしかなく、腑に落ちる答えがでない。幸運にも西洋圏へと戻った彼は、そこに留まりながら野蛮の地で立証できなかった命題について考えたに違いない。書く事、独白する事もまた自己の解体だ。筆を置いた後、彼は快楽へと辿りつくことができたのだろうか。2013/10/24
おおた
18
人喰い人種に囚われた見習い水夫が、10年間彼らを観察した後になぜか解放されてスペイン人社会に戻される。その後、学のない主人公が勉強し成功して、過去を回想するという形式。インディオたちは普段は慎み深いが、夏が来ると乱交パーティ&人喰いで乱痴気騒ぎ。そのギャップを第三者の内省的な視点で綴る。しかし、語り手が参加しない理由は明記されず、カニバリズムの要因がただの想像からインディオの都合の良い解釈に至って、一人よがりの感を免れない。精緻な描写と裏腹に腑に落ちないラストであった。2013/07/07
アドソ
17
若干のきっかけはあったにしても、これがフィクションだとは信じがたいほどリアルな描写。そのリアルさは確かに近代日本人から見ると全然リアルじゃないんだけど。語り手のこの生活はいつまで続くのかと思いきや、早々に自国に帰ることができ、過ぎし日の解釈に充てられる。近代社会だけが人間の取りうるべき姿ではない、と警告するようで、作者の想像力には脱帽。2015/08/06
erierif
16
孤児が船乗りとして成長しインディオに捕まり10年暮らしまた文明社会に戻り教育をうけ旅回りの演劇を続けた後、考察する後半がとても面白い。おぞましくも野蛮な儀式や風変わりな言語、習慣全てがあるがままに受けとめられていく。自然や土地の力、野生の力を西洋文明社会と対比して考察されている気がした。2013/08/29
-
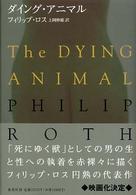
- 和書
- ダイング・アニマル








