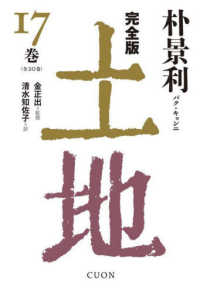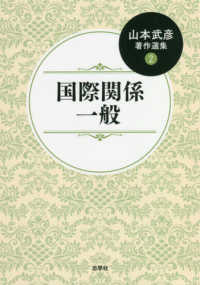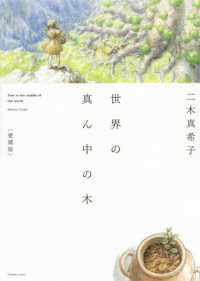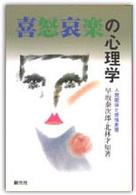内容説明
動乱の時代を生きた思想家バタイユは、文学にどのような可能性をみていたのか。他者との不可能な交流の場としての文学という視点で、バタイユの文学観を明るみにだし、新たなコミュニケーションの形態を提示する試み。
目次
序章 『文学と悪』(一九五七年)
第1章 陰画の文学
第2章 不一致の一致
第3章 「友愛」(一九四〇年)
第4章 『内的体験』(一九四三年)
終章 ある「私の死」への追悼の試み
著者等紹介
福島勲[フクシマイサオ]
1970年、埼玉県に生まれる。ジュネーヴ大学留学(DES取得)を経て、東京大学大学院人文社会系研究科フランス語フランス文学専門分野博士課程修了。博士(文学)。2007年より、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻助教。2011年4月より、北九州市立大学文学部比較文化学科准教授。専攻、フランス文学・思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel
2
作家は共同体の帰属を諦めて、社会に背を向ける。ただし、「悪」であり「有罪」である作家は、同時に「選ばれた者」でもあり、来るべき「超道徳」を提示するものでもある。バタイユが提示した超道徳は、「踏み込むことのできない他人の聖域」を認めたうえで、テクストを介した「交流」によって他者との対立を拒絶する世界の見方だった。とまとめてみた。第一章のデリダらによるバタイユ批判のまとめ方や、序章におけるデュラスを絡めた導入の仕方がわかりやすかった。そしてだからこそなんだけれど、結果として見いだされる世界観に不満が残る。2018/06/11
1
再読。やっぱり再読しても素晴らしい。バタイユの思想がエログロ =禁止/侵犯という文脈(恐らく、それも一面ではあるのだが)から目を開かされた本。バタイユを文学のコミュニケーションという側面から読み取るのだが、無神学大全という中期の「孤独」な「書くこと」のうちに、むしろこの絶対的「孤独」=「ずれ」「差異」の内に分有=交流の可能性を見る。「ひとり/ひとり」である私たちが、「ひとりひとり」というスラッシュを抜かれる「瞬間」、恐らくここにコミュニズムの「幸運な賭け」が存在する。2024/02/25
トックン
0
「交流(コミュニカシオン)」をキー概念としながらバタイユのテクスト論、コミュニケーション論をわかりやすく解説した本。2013/02/06